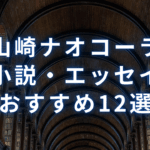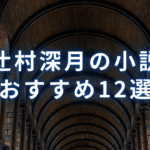- 不確実な現実では、上手くいかないことを前提に柔軟に対応する「工作の思考」が、人生を生き抜く鍵。
- 森博嗣の少年時代からの実行力と、知識ではなく「道理」を理解する姿勢が、天才的な創造性を生む。
- 技術や創作では、謙虚さ、持久力、そして過程を楽しむ自給自足の楽しさが重要で、工業と芸術の価値の違いの認識も。
- 人生を「工作」として楽しむために、言葉の単純化を避け、オリジナリティを守り、自己評価を重視。
森博嗣の略歴・経歴
森博嗣(もり・ひろし、1957年~)
小説家、工学者。
愛知県の生まれ。東海中学校・高等学校、名古屋大学工学部建築学科を卒業。名古屋大学大学院修士課程を修了。三重大学、名古屋大学で勤務。1990年に工学博士(名古屋大学)の学位を取得。1996年に『すべてがFになる』で第1回メフィスト賞を受賞しデビュー。
『創るセンス 工作の思考』の目次
まえがき
第1章 工作少年の時代
第2章 最近感じる若者の技術離れ
第3章 技術者に要求されるセンス
第4章 もの作りのセンスを育てるには
第5章 創作のセンスが産み出す価値
あとがき
『創るセンス 工作の思考』の概要・内容
2010年2月22日に第一刷が発行。集英社新書。204ページ。
『創るセンス 工作の思考』の要約・感想
- 上手くいかないことが「普通」であるという前提
- 実行力が生み出す天才の原点
- 「知識」と「道理」の決定的な違い
- 技術に対する謙虚さと畏敬の念
- 柔軟な発想を生むのは「持久力」である
- 小説家デビューに見る戦略的思考
- 創作の喜びと想定外の展開
- 「工業」と「芸術」の価値の所在
- 楽しさは「自給自足」するものである
- 言葉による「単純化」の危険性
- 「読まない」ことで守られるオリジナリティ
- 少年時代の「わくわく」を回収する人生
- 自己評価という絶対的な自信
- 総論:人生という工作を楽しむために
あなたは、自分の人生をどのように「設計」しているだろうか。
あるいは、設計図通りにいかない現実に、苛立ちを覚えてはいないだろうか。
世の中には、緻密なマニュアルや成功法則が溢れている。
しかし、どれだけ情報を集め、完璧な計画を立てたつもりでも、想定外の事態は必ず起こる。
そんな不確実な現代において、私たちが持つべき指針とは何なのか。
今回紹介する書籍は、小説家であり工学博士でもある森博嗣(もり・ひろし、1957年~)の著書、『創るセンス 工作の思考』である。
森博嗣といえば、『すべてがFになる』で第1回メフィスト賞を受賞し、鮮烈なデビューを果たしたミステリ作家として知られている。
その一方で、彼は名古屋大学工学部建築学科を卒業し、同大学院で修士課程を修了、さらに工学博士の学位を持つ「元・国立大学助教授」という経歴を持つ。
本書は、そんな「理系ミステリィの巨匠」が、自身の原点である「工作少年」としての視点から、もの作り、ひいては「生き方」における思考法を語り尽くした一冊である。
対象となるのは、これから社会に出る学生や、日々の仕事に追われる現代人である。
単なる技術論ではない。
これは、予測不能な現実を楽しみ、自分自身の価値を「創る」ための哲学書である。
本書を通して、表面的な知識ではない「ものの道理」と、森博嗣という天才の思考回路を紐解いていきたい。
上手くいかないことが「普通」であるという前提
私たちは、何かに取り組む際、無意識のうちに「上手くいくこと」を前提に行動していないだろうか。
計画通りに進むのが当たり前。
失敗はイレギュラーな事態。
そう考えているからこそ、予期せぬトラブルに直面したとき、パニックに陥り、足を止めてしまう。
しかし、森博嗣の認識は根本から異なる。
彼は、工作という経験を通じて、世界の「物理的な現実」を骨の髄まで理解しているからだ。
簡単に結論を書いてしまえば、「上手くいかないことが問題」なのではなく、「上手くいかないことが普通」なのだ。(P.11「まえがき」)
この言葉は、本書の中で形を変え、何度も繰り返し語られる重要なテーマである。
現実世界には、無限に近い不確定要素が存在する。
材料の強度、気温や湿度、道具の摩耗、そして自分自身の体調や手元の狂い。
これらすべてを完全にコントロールすることなど、人間には不可能である。
どれだけ綿密に準備をし、完璧な設計図を描いたとしても、予想外のことが生じるのが「自然の摂理」なのだ。
だからこそ、「上手くいかないのが通常(デフォルト)」として設定しておかなければならない。
この基本姿勢を持っているか否かで、トラブルへの対処能力に雲泥の差が生まれる。
失敗を「異常事態」と捉える人は、そこで思考停止に陥るか、誰かのせいにしてしまう。
しかし、失敗を「通常運転」と捉える人は、「さて、どう修正しようか」と即座に次の一手を打てる。
予想外のことが起きた場合に、柔軟に、臨機応変に対処すること。
この「工作の思考」こそが、不透明な現代社会を生き抜くための最強の武器となるのである。
これはビジネスにおいても、人間関係においても同様だ。
絶対の安全や確実な未来など存在しない。
その前提に立ったとき、私たちは初めて、本当の意味での「準備」ができるのである。
実行力が生み出す天才の原点
森博嗣という人物を語る上で、外せないエピソードがある。
それは彼がまだ少年だった頃の「工作」の規模感だ。
通常の小学生が作る工作といえば、本棚や貯金箱といったレベルだろう。
しかし、彼の好奇心と実行力は、常軌を逸していた。
小学4年生の夏休みには、自分とほぼ同じ身長のロボットを作った。(P.25「工作少年の時代」)
小学4年生、つまり10歳か11歳の少年である。
その少年が、自分の身長と同じ程度の大きさのロボットを設計し、作り上げたというのだ。
しかもそれは単なる張りぼてではない。
リモコン操作によって、前後左右に動かすことができる「機械」であった。
モーターの動力をどのように車輪に伝えるか。
電池ボックスをどう配置するか。
重心のバランスをどう取るか。
等身大のロボットを動かすためには、物理的な課題が山積していたはずである。
それを小学生が独力で解決し、完成させたという事実は、驚愕に値する。
これは、彼が単なる「夢想家」ではなく、圧倒的な「実行者」であることを示している。
頭の中で「こんなロボットがあったらいいな」と空想する子供は多い。
しかし、実際に材料を集め、手を動かし、失敗を繰り返しながら形にする子供は稀有だ。
この「思いついたら、作る」という即断即決と実行力。
そして、完成までこぎつける執念。
こうした素質が、後の工学博士・森博嗣を作り、そして驚異的なペースで作品を生み出し続ける小説家・森博嗣を形作ったことは疑いようがない。
彼の思考の根底には、常に「具体的に手を動かす」というリアリズムがあるのだ。
「知識」と「道理」の決定的な違い
現代は「情報」の時代である。
インターネットで検索すれば、あらゆる知識が瞬時に手に入る。
マニュアルを読めば、誰でもそれなりの成果が出せるようになった。
しかし、森博嗣は警鐘を鳴らす。
それは本当に「理解した」と言えるのだろうか、と。
優れた技術者とは、知識が豊富なのではなく、ものの道理を知っている人のことだ。どうも、現代は本当に懇切丁寧なマニュアル社会になった。言葉が多すぎる(情報過多だ)から、言葉に埋もれてしまうのだと思う。意識して防衛していないと、頭の中がすぐに言葉まみれになってしまう。(P.69「最近感じる若者の技術離れ」)
ここで語られているのは、「知識」と「道理」の決定的な違いである。
知識とは、単なる情報の断片、つまり「点」である。
一方で、道理とは、物事がなぜそうなるのかという理屈、つまり「線」や「面」としての理解である。
マニュアルに従って操作ができることと、その機械が動く原理を理解していることは、似て非なるものだ。
現代人は、あまりにも表面的な「言葉」や「マニュアル」を重要視しすぎている傾向がある。
言葉は便利だが、同時に思考を停止させる麻薬でもある。
「言葉に埋もれる」という表現は、非常に鋭い現代社会への批評だ。
私たちは、分かった気になるための言葉を消費しているに過ぎないのではないか。
観念的な言葉遊びではなく、現実的に「ものがどう動くのか」「なぜ失敗するのか」という物理的な法則(道理)を肌感覚で知ること。
情報過多な時代だからこそ、意識的に情報の流入を制限し、自分の頭で「道理」を考える時間を確保する防衛策が必要なのだ。
技術に対する謙虚さと畏敬の念
科学技術は、人類に繁栄をもたらした。
技術とは、その科学の知恵を社会に還元するための道具である。いくら進化をしても、その道具を使う者は、常に謙虚で慎重に努め、自分が失敗する可能性や、考えが及ばない範囲があることを、自覚自問し続けなければならない。(P.104「技術者に要求されるセンス」)
人類の歴史を振り返れば、農耕や牧畜の始まりは、将来の飢餓という不安への対抗策であった。
自然の脅威を予測し、制御するために科学が生まれ、発展してきた。
しかし、どれだけ科学が発展しても、それは「道具」に過ぎない。
その道具を使う人間が、全能感を抱いた瞬間に事故は起きる。
「想定外」という言葉で責任を回避しようとする姿勢は、技術者としてあるまじき態度だ。
技術が社会に還元され、人々の安全を担保するものである以上、そこには絶対的な謙虚さが求められる。
「自分は間違えるかもしれない」。
「自分の計算には見落としがあるかもしれない」。
そうやって自覚自問し続ける姿勢こそが、真のプロフェッショナルの条件である。
これは技術者に限った話ではない。
どのような仕事であれ、自分の能力や計画を過信せず、常に「考えが及ばない範囲」への想像力を残しておくこと。
その謙虚な学びの姿勢が、結果として大きな事故や失敗を防ぐ唯一の手立てとなるのである。
柔軟な発想を生むのは「持久力」である
「センス」や「発想力」という言葉を聞くと、私たちは天啓のような「ひらめき」をイメージしがちだ。
しかし、本書で語られる「センス」の正体は、もっと泥臭く、地道なものである。
柔軟な発想というのは、突然思いつくものではなく、いつも可能性を探す目で見ている、その集積の中から芽生えるのである。(P.117「技術者に要求されるセンス」)
柔軟な発想とは、瞬発力ではない。
それは「持久力」である。
常日頃から、「もしかしたらこうかもしれない」「別のやり方があるかもしれない」と可能性を探り続ける、絶え間ない思考の鍛錬。
その膨大な思考の集積があって初めて、ある瞬間に「答え」が浮かび上がるのだ。
何も考えていない人間に、突然アイデアが降ってくることはない。
森博嗣のユニークな作品群や、意表を突くトリックの数々も、天才の思いつきではなく、日常的な観察と考察の蓄積によるものなのだろう。
私たちは結果だけを見て「天才のひらめき」と呼ぶが、その背景には、常に世界を観察し続ける「目」の持続力があることを忘れてはならない。
小説家デビューに見る戦略的思考
森博嗣が小説家になったきっかけは有名だ。
それは「趣味の鉄道模型(庭園鉄道)を作る資金が欲しかったから」である。
動機は不純に見えるかもしれないが、そのアプローチは極めて戦略的かつ工学的だった。
書くならばシリーズにして、何冊も出版する計画で臨もう。処女作からそれを念頭において、最低限10作くらいは続くような物語世界を想定した。(P.124「技術者に要求されるセンス」)
多くの作家志望者は、まず「最高の一作」を書こうとする。
しかし、森博嗣は違った。
最初から「シリーズ化」を前提とし、10作書くつもりで設計したのである。
なぜなら、その方が「儲かるから」であり、効率が良いからだ。
単発で終われば、またゼロから設定を作り直さなければならない。
しかしシリーズものであれば、世界観やキャラクターを資産として使い回せる。
実際、彼はデビュー作『すべてがFになる』の前に、すでに数作を書き上げていたという逸話がある。
出版された順番としては『すべてがFになる』が最初だが、執筆順では4作目にあたる。
つまり、デビュー時点で既に「前日譚」を含む壮大な物語が原稿として存在していたのだ。
この圧倒的な俯瞰的視点は、まさに建築や工学のプロジェクトマネジメントそのものである。
さらに興味深いのは、彼が「設計図(プロット)は作らない」と公言している点だ。
全体的な戦略は緻密に計算しつつ、個々の物語の展開においては「ライブ感」を重視する。
設計図通りに文字を埋めるだけの作業になってしまうと、それは「単純労働」になり、楽しみが失われるからだ。
大量の文章を書き続け、長期的に継続するためには、著者自身が「楽しむ」仕組みが必要不可欠である。
この「戦略的な枠組み」と「即興的な楽しみ」のバランスこそが、森博嗣の多作を支えるエンジンの正体である。
創作の喜びと想定外の展開
小説執筆における「楽しみ」について、彼はさらに具体的に語っている。
いちおう、最初に登場人物表を作るけれど、全然そのとおりにはいかない。性別が変わったり、突然現れる想定外の人がいたり、逆に最後まで出てこない人がいたりする。書くこと自体がスリリングで、思いのほか楽しい。はっきりいって、小説を読むよりも楽しい。(P.125「技術者に要求されるセンス」)
登場人物表を作っても、書いていく途中で変化しまくる。
キャラクターが勝手に動き出し、作者の想定を超えていく。
この「制御不能な感覚」を楽しんでいる様子が伝わってくる。
森博嗣にとって、小説を書くことは、あらかじめ決まった結末へ向かう作業ではなく、未知の領域への探索なのだ。
「小説を読むよりも楽しい」という言葉は重要だ。
消費する側(読書)よりも、生産する側(執筆)の方が、遥かに刺激的で喜びが大きい。
これは、あらゆるクリエイティブな活動に通じる真理だろう。
長期的な継続や、大量生産を行うためには、ストイックな努力だけでは限界がある。
そこには、本人にしか分からない「快楽」や「喜び」がなければならない。
後のエッセイでは、小説執筆に対してドライな発言も目立つようになる森博嗣だが、少なくとも初期においては、書くことそのものを純粋に楽しんでいたことが窺える。
仕事や創作を長く続ける秘訣は、そのプロセスの中に「自分だけの遊び」を見つけることなのかもしれない。
「工業」と「芸術」の価値の所在
本書の中でも特に白眉と言えるのが、工業と芸術の違いについての定義である。
工業と芸術の違いは、作ったものに価値を見出すか、作る過程に価値を見出すか、の違いで区別される。工業はあくまでも作品に価値がある。芸術は、作る過程で作者が得た感覚がすべてであって、出来上がった作品は単なる残骸、あるいは思い出のシンボルでしかない。(P.126「技術者に要求されるセンス」)
この視点は、現代のWebビジネスやコンテンツ制作を考える上でも非常に示唆に富んでいる。
工業製品において重要なのは「再現性」と「均質性」である。
誰が作っても同じ性能でなければならないし、コピー(複製)しても価値は変わらない。
むしろ、コピーできることにこそ工業の強みがある。
Webサービスやアプリのようなビジネスモデルは、この「工業的アプローチ」に近い。
一度仕組みを作れば、それは何度複製されてもユーザーに同じ価値を提供する。
一方で、芸術は「一回性」に宿る。
作者がその瞬間に感じたこと、苦悩や発見といったプロセスそのものに価値の本質がある。
だからこそ、出来上がった作品は「残骸」に過ぎないという過激な表現がなされる。
芸術作品においてコピーが「贋作」として価値を失うのは、そこにオリジナルのプロセス(魂の痕跡)が存在しないからだ。
自分が作っているものは、工業製品(結果に価値がある)なのか、芸術作品(過程に価値がある)なのか。
この問いを持つことで、モノ作りへの向き合い方は大きく変わるはずだ。
楽しさは「自給自足」するものである
私たちはつい、誰かが自分を楽しませてくれることを期待してしまう。
面白い映画、楽しいイベント、魅力的なパートナー。
しかし、森博嗣は「楽しさ」を受動的なものとは捉えていない。
本当の楽しさは、自分の中から湧き出るもの、自分で作るものである。だから、楽しさの作り方をまず覚えなければならない。(P.136「もの作りのセンスを育てるには」)
人から与えられた楽しさは、消費財であり、一時的な刺激に過ぎない。
賞味期限が切れれば、また次の刺激を求めて彷徨うことになる。
一方で、自分の内側から湧き出る楽しさ、自分で工夫して作り出した楽しさは、持続的であり、枯渇することがない。
これは人間関係、特に家族や夫婦関係においても同様だ。
「私を幸せにしてほしい」と相手に依存する関係は脆い。
それぞれが自立して楽しみを作り出せる人間であって初めて、健全な共有が可能になる。
「楽しさの作り方を覚える」というのは、大人が身につけるべき最も重要な教養の一つかもしれない。
誰かから貰おうとするのではなく、自分の手で作り出す。
それはまさに「工作」の精神そのものである。
言葉による「単純化」の危険性
言葉は便利だ。
複雑な事象を切り取り、ラベルを貼り、分かった気にさせてくれる。
しかし、現実は言葉よりも遥かに高解像度である。
しかし、現実の人生も、現実の工作も、はるかに多種で、複雑で、言葉とはまったく反対といっても良いくらいである。結局、「言葉にまとめられるもの」ではない。(P.157「もの作りのセンスを育てるには」)
実際の工作では、素材の反りや歪み、手触りといった言語化できない微細な要素が結果を左右する。
人生も同様だ。
「成功」「失敗」「幸福」「不幸」といった単純な言葉で割り切れるほど、私たちの生は単純ではない。
森博嗣は、安易な「要約」や「まとめ」を警戒する。
言葉でまとめてしまうことで、そこにあるはずの豊かさや複雑なノイズが削ぎ落とされてしまうからだ。
簡単に言葉でまとめて、分かった気になってはいけない。
納得した気になって思考を停止させてはいけない。
「言葉にできない部分」にこそ、現実の手触りと本質が隠されている。
私たちは、分かりやすいキャッチコピーや見出しに飛びつきがちだが、その背後にある割り切れない複雑さに耐える知性を持つべきだろう。
「読まない」ことで守られるオリジナリティ
作家であれば、多読家であることが推奨されるのが一般的だ。
しかし、森博嗣のスタンスはここでも独特である。
僕は、工作のように技術優先のものでは、優れた他者の作品を多く見ることが自分のためになると考えているけれど、小説のように技術が優先しない創作においては、他者の作品をできるかぎり読まない方が良いと感じている。(P.179「創作のセンスが産み出す価値」)
工作や工学においては、先人の技術を模倣し、学ぶことが必須である。
それは「技術」が積み上げ式のものであり、正解が存在する世界だからだ。
しかし、小説のような創作においては、技術よりも「その人らしさ(オリジナリティ)」が重要になる。
他者の作品を読みすぎると、無意識のうちに影響を受け、自分の文体や発想が侵食されてしまうリスクがある。
森博嗣は、自分自身の内なる声を純粋に出力するために、あえて情報を遮断しているのだ。
「小説は技術が優先しない」という言葉には議論の余地があるかもしれない。
一般人からすれば、小説にも高度な技術が必要に見える。
しかし、卓越した能力を持つ森博嗣の目から見れば、小説の本質は技術的な巧拙ではなく、もっと個人的で感覚的な部分にあるということなのだろう。
彼は「あまり小説を読んでいない」と公言している。
だからこそ、既存の文学の枠にとらわれない、あれほど自由で新しいミステリを書くことができたのだ。
インプット過多で身動きが取れなくなっている現代人にとって、この「あえて入れない」という勇気は学ぶべき点が多い。
少年時代の「わくわく」を回収する人生
工学博士になり、大学助教授になり、ベストセラー作家になり、莫大な富を得た。
客観的に見れば「成功者」の象徴のような森博嗣だが、彼の行動原理は驚くほどシンプルだ。
結局は、少年時代のあの「わくわく」を、この歳になっても求めているのである。(P.189「創作のセンスが産み出す価値」)
すべての活動は、少年時代に感じた工作の興奮、あの純粋な「わくわく」を再現するための手段に過ぎない。
大人になると、私たちは「効率」や「利益」、「世間体」といった不純物を混ぜて判断しがちだ。
しかし、人の根源的な駆動力は、子供の頃に感じた初期衝動にある。
彼が庭園鉄道を作り、飛行機を飛ばし、小説を書くのは、高尚な目的のためではない。
ただ、少年の頃の欲望に忠実であり続けているだけなのだ。
この結論に行き着くことには、ある種の救いがある。
私たちは、もっと自分の「わくわく」に素直になっていい。
それが、人生を豊かに生きるための最短ルートなのだから。
自己評価という絶対的な自信
最後に、森博嗣の強靭なメンタリティを象徴する言葉を紹介したい。
褒められてもそんなに嬉しくないし、貶されてもそんなに悔しくはない。それはやはり、自分の評価の方がずっと正確だという確信があったからだ。(P.194「創作のセンスが産み出す価値」)
他者の評価に一喜一憂しない。
これは、単なる強がりではなく、自分自身への圧倒的な信頼と、客観的な自己分析に基づいている。
自分がどれだけ準備し、どれだけ丁寧に作業し、どこで手を抜いたか。
そのプロセスを最も詳細に知っているのは、紛れもなく自分自身である。
他人は結果しか見ない。
しかし、自分は過程を知っている。
だから、自分の評価の方が、他人の無責任な賞賛や批判よりも、遥かに正確で精緻なのだ。
この達観した境地に至るには、自分自身を欺かない誠実な仕事(工作)を積み重ねる必要がある。
自分で自分を「よくやった」と認められるか。
あるいは「ここはダメだった」と冷静に分析できるか。
その絶対的な基準を自分の中に持つことができれば、世間のノイズに惑わされることなく、淡々と自分の道を歩んでいけるはずだ。
総論:人生という工作を楽しむために
『創るセンス 工作の思考』は、タイトルの通り「工作」の本でありながら、その実、極めて実践的な人生の攻略本である。
最初から上手くいくとは思ってはいけない。
予想外のことは必ず起きる。
だからこそ、しっかりと準備をし、謙虚に学び、そして実際に手を動かす。
森博嗣の思考は、ドライで合理的でありながら、その根底には「楽しむこと」への情熱が脈打っている。
知識ではなく道理を。
結果ではなく過程を。
他人の評価ではなく自己評価を。
これらの指針は、情報と他者の視線に振り回されがちな私たちに、確かな足場を与えてくれる。
読みやすく、分かりやすい語り口の中に、本質的な智慧が詰まった一冊。
これから自分の人生を「創って」いこうとするすべての人に、強くおすすめしたい名著である。
忘れないようにしよう。
人生は、思い通りにいかないからこそ、工作しがいがあるのだと。
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:エッセイや随筆など
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:推理小説など読む順番も
- 森博嗣『夢の叶え方を知っていますか?』要約・感想
- 森博嗣『作家の収支』要約・感想
- 森博嗣『小説家という職業』要約・感想
- 森博嗣『新版 お金の減らし方』要約・感想
- 森博嗣『自分探しと楽しさについて』要約・感想
- 森博嗣『自由をつくる 自在に生きる』要約・感想
- 森博嗣『「やりがいのある仕事」という幻想』要約・感想
- 森博嗣『孤独の価値』要約・感想
- 森博嗣『読書の価値』要約・感想
- 森博嗣『アンチ整理術』要約・感想
- 森博嗣『勉強の価値』要約・感想
- 森博嗣『諦めの価値』要約・感想
- 森博嗣『悲観する力』要約・感想
- 森博嗣『集中力はいらない』要約・感想
- 【選書】畑村洋太郎のおすすめの本・書籍12選:失敗学、数学、わかる技術
- 畑村洋太郎『失敗学のすすめ』要約・感想
- 中島義道『働くことがイヤな人のための本』要約・感想
- ジョナサン・マレシック『なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか』要約・感想
- ロバート・L・ハイルブローナー『入門経済思想史 世俗の思想家たち』要約・感想
- ジョン・ウッド『マイクロソフトでは出会えなかった天職』要約・感想
- スコット・ギャロウェイ『ニューヨーク大学人気講義 HAPPINESS』要約・感想
- ピーター・ティール『ZERO to ONE』要約・感想
- G・M・ワインバーグ『コンサルタントの秘密』要約・感想
- 中村哲『わたしは「セロ弾きのゴーシュ」』要約・感想
- 今北純一『仕事で成長したい5%の日本人へ』要約・感想
- 冲方丁『天地明察』あらすじ・感想
- 司馬遼太郎『空海の風景』あらすじ・感想
- 瀧本哲史『僕は君たちに武器を配りたい』要約・感想
- 神津朝夫『知っておきたいマルクス「資本論」』要約・感想
- 木暮太一『働き方の損益分岐点』要約・感想
- 本多静六『お金・仕事に満足し、人の信頼を得る法』要約・感想
- 竹内均『人生のヒント・仕事の知恵』要約・感想
- 藤原正彦『天才の栄光と挫折』要約・感想
- 邱永漢『生き方の原則』要約・感想
- 高橋弘樹/日経テレ東大学『なんで会社辞めたんですか?』要約・感想
- 鷲田清一『岐路の前にいる君たちに』あらすじ・感想
- 齋藤孝『座右のニーチェ』要約・感想
- 齋藤孝『日本人の闘い方』要約・感想
- 齋藤孝『最強の人生指南書』要約・感想
書籍紹介
関連書籍