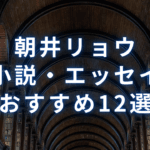- 森博嗣は感情ではなく理想を基準に論理的に行動し、俯瞰力でビジネスを構築する思考を提唱。
- デビュー前から長期戦略を立案し、編集者・宇山秀雄との出会いで加速、批判をデータとして活用して創作を進化。
- 読者の期待を裏切り、独自のマーケティングを実践し、出版業界の慣習に論理で対抗。
- 執筆を写真撮影のように捉え、タイトルを核にし、変化の諦念を受け入れ、世の中への絶望と希望を冷徹な知性で生き抜く術を示す。
森博嗣の略歴・経歴
森博嗣(もり・ひろし、1957年~)
小説家、工学者。
愛知県の生まれ。東海中学校・高等学校、名古屋大学工学部建築学科を卒業。名古屋大学大学院修士課程を修了。三重大学、名古屋大学で勤務。1990年に工学博士(名古屋大学)の学位を取得。1996年に『すべてがFになる』で第1回メフィスト賞を受賞しデビュー。
『小説家という職業』の目次
まえがき
1章 小説家になった経緯と戦略
2章 小説家になったあとの心構え
3章 出版界の問題と将来
4章 創作というビジネスの展望
5章 小説執筆のディテール
あとがき
『小説家という職業』の概要・内容
2010年6月22日に第一刷が発行。集英社新書。199ページ。
『小説家という職業』の要約・感想
- 感情ではなく理想を拠点にする思考法
- デビュー前から完成していた長期戦略
- 名編集者との運命的な出会いと加速
- 批判的意見をデータとして活用する
- 期待に応えるのではなく裏切るマーケティング
- 自信の欠如としての怒り
- 出版業界の慣習との闘争
- 売れることと評価されることのパラドックス
- 写真を撮るように文章を書く
- タイトルという最強の要約
- 速読というナンセンス
- 変化を見送るという諦念と決断
- 人間への絶望と僅かな希望
- 総論:生き残るための冷徹な知性
本の題名は『小説家という職業』。
著者は、国立大学の工学部助教授として勤務しながら、圧倒的なスピードとクオリティでミステリ界を席巻し、今なお第一線で活躍し続ける森博嗣である。
本書は、単なる小説家のエッセイではない。
これは、一人の研究者が、いかにして「小説家」という職業をハックし、ビジネスとして成立させ、そして持続可能なシステムとして構築したかを記した、極めて実践的なビジネス書であり、戦略書である。
あるいは、生き方そのものを問う哲学書と言っても過言ではない。
私がこの本を読み込んで感じたことは、森博嗣という人物が持つ、底知れない「俯瞰力」の凄みである。
彼は、小説を書くという行為を、単なる芸術的な発露や自己表現の場とは捉えていない。
もっとドライで、もっとシステマチックな「生産活動」として捉えているのだ。
その思考のプロセスは、文学部出身の作家が語るそれとは全く異質であり、だからこそ、我々が日々の仕事や生活に応用できる普遍的な真理に満ちている。
本記事では、この『小説家という職業』をテキストとして、森博嗣の思考回路を分解し、我々がいかにして「プロフェッショナル」として振る舞うべきかを、詳細に解説していく。
これから社会に出ようとする若者も、組織の論理に疲弊している中堅も、あるいは独立独歩を目指す野心家も、必ずや何らかの「武器」を得ることができるはずである。
それでは、森博嗣の思考の森へと足を踏み入れてみよう。
感情ではなく理想を拠点にする思考法
多くの人は、職場の人間関係や上司の評価、あるいは世間の評判といった「他者の感情」を基準に行動を選択してしまう。
しかし、森博嗣はそれを明確に否定する。
彼にとって重要なのは、自分が掲げた「理想」であり、その理想にいかに近づくかという一点のみである。
周りの人間に好かれるために仕事をしているのではない。理想があれば、その理想を拠り所にして行動する。できるかぎりそれに近づく方向を目指す。そんな甘い方針を本気で掲げるのが、僕のやり方である。(P.15「まえがき」)
この言葉の切れ味はどうだろうか。
組織の中で自分の立場を守ることに汲々とし、本質を見失っている現代人に対する強烈なアンチテーゼである。
森博嗣は、世の中のニーズを高い視点から俯瞰し、先手を的確に打っていくことこそが重要だと主張している。
ここには、「世間の厳しさ」や「大人の事情」といった言い訳が入る余地はない。
「世間の厳しさなんて知ったことではない」と明確に後述もしている。
しかし、これは単なる傲慢ではない。
より広い視野でビジネスの構造を捉え、自分のなすべきことを論理的に導き出した結果なのである。
当時、国立大学の研究者という立場でありながら、ここまでシビアに「商売」としての執筆活動を考えていたことには驚嘆するほかない。
彼の思考は常にロジカルであり、感情に流されることがない。
自分の理想を「甘い方針」と謙遜して表現しているが、その実、それを貫徹するためには並々ならぬ意志の強さと、冷徹な計算が必要であることは言うまでもない。
我々は往々にして、目の前の仕事に忙殺され、自分が本来目指していた理想を見失いがちである。
しかし、プロフェッショナルとは、環境に文句を言うことではなく、環境を俯瞰し、自分の理想を実現するための最適解を常に模索し続ける存在のことを指すのかもしれない。
森博嗣のこの姿勢は、どのような職種であれ、一流と呼ばれる人間に共通する資質であると言えるだろう。
デビュー前から完成していた長期戦略
森博嗣が小説家としてデビューした経緯は、あまりにも有名であり、かつ異常である。
彼は、趣味で模型を作るための資金稼ぎとして、アルバイト感覚で小説を書き始めた。
しかし、その書き方は、素人が思いつきで書くようなものではなかった。
最初から綿密な事業計画書のような「戦略」が存在していたのである。
まず5作くらいは書くつもりだったので、最初はオーソドックスに大人しく始めて、2作めで少しだけ個性を出し、3作めで技巧的な別の面を見せる。そして4作めでようやく全力を出し、5作めでは、それをさらに凌ぐようなものを書こう。このような抽象的な計画を立てたのである。(P.40「1章 小説家になった経緯と戦略」)
驚くべきことに、彼はデビューする前から、5作目までの作品の傾向と、作家としてのブランディングの推移を完全に設計していたのである。
最初からここまで物語の構成と、読者への提示の仕方を考えていた作家が、果たしてどれほど存在するだろうか。
多くの小説家志望者は、とりあえず渾身の1作を書き上げ、それを賞に応募することで精一杯である。
しかし、森博嗣は違った。
彼は、作家としてのキャリア全体を俯瞰し、長期的な視点で「森博嗣」という商品をどのように市場に浸透させていくかを計算していたのである。
これは、ビジネスで言えば、新製品のローンチ戦略そのものである。
最初は市場に受け入れられやすいベーシックなモデルを投入し、徐々にブランドの個性を出し、固定ファンがついたところでハイエンドなモデルを投入する。
まさにマーケティングの定石を、小説の世界で実践しようとしていたのだ。
小説家予備軍の人たちの中で、ここまで考えている人は皆無に近いだろう。
いや、たとえプロの小説家であっても、これをデビュー前に構想し、さらに現実に落とし込んで実行できる人は極めて稀なはず。
裏を返せば、プロを目指すのであれば、これくらいのことは考えておけ、という森博嗣からのメッセージとも受け取れる。
彼が成功したのは、単に才能があったからだけではない。
才能を運用するための「戦略」が優れていたからこそ、これほどの成功を収めることができたのである。
名編集者との運命的な出会いと加速
森博嗣の計画は完璧に見えたが、現実は彼の予想を上回るスピードで動き出した。
彼が1作目を出版社に送り、大学の研究の合間を縫って「1ヶ月に1作」という森博嗣の言う「穏やかなスケジュール」で2作目を書き上げた頃、事態は急展開を迎える。
そして、驚いたことに、まだできてもいない4作めを最初に出版する、と編集長が言い出したのである。 この編集長というのは宇山秀雄氏という、この分野では有名な人だった(残念ながら2006年に亡くなられた)。(P.43「1章 小説家になった経緯と戦略」)
ここで登場する人物こそ、講談社の伝説的な編集者、宇山秀雄(うやま・ひでお、1944年~2006年)である。
宇山秀雄は、京都府京都市の出身で、同志社大学を卒業後、三井物産を経て講談社に入社した経歴を持つ。
彼は星新一との関係も深く、綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸、歌野晶午らをデビューさせた、まさに新本格ミステリの仕掛け人とも言える存在である。
後にメフィスト賞を創設し、京極夏彦、舞城王太郎、西尾維新らの発掘に関わったことでも知られている。
その宇山秀雄が、まだ書かれてもいない「4作目」の構想を聞き、それをデビュー作として出版することを即決したのだ。
これが、森博嗣のデビュー作となり、大ベストセラーとなった『すべてがFになる』である。
森博嗣の戦略的思考も凄まじいが、その原石の輝きを一瞬で見抜き、計画を修正させてまで最適な売り出し方を提案した宇山秀雄の判断もまた、恐ろしいほどである。
編集者という職業が、単なる原稿整理係ではなく、作家と共にコンテンツを作り上げるプロデューサーであることを証明するエピソードである。
森博嗣という特異な才能と、宇山秀雄という稀代の目利きが出会ったことは、日本のミステリ界にとって最大の幸福だったと言えるだろう。
批判的意見をデータとして活用する
小説家になった後も、森博嗣の「研究者」としてのスタンスは変わらない。
彼は、読者からのフィードバックを、感情的なメッセージとしてではなく、貴重な「データ」として処理し続けた。
さらに、メール以外にも、自分のブログで本の感想を書く人が急増した。僕はこれらもできるかぎり目を通すようにしている。メールで届くものよりも、素直な意見、または批判的な意見に触れることができるので、データとして価値が高い。(P.71「2章 小説家になったあとの心構え」)
森博嗣は、自身のメールアドレスを公開し、届いた感想に対して返信を行うという活動を12年ほど続けていたという。
ピーク時には1日に200通ものメールが届いていたというから驚きである。
彼はそれらを効率的に処理しながら、同時にインターネット上のブログなどに書かれた感想もチェックしていた。
ここで重要なのは、彼が「批判的な意見」こそデータとして価値が高いと判断している点である。
普通の人間であれば、自分の作品を批判されれば傷つき、目を背けたくなるものである。
しかし、森博嗣は違う。
褒める言葉は、自己を隠した装飾的なコミュニケーションになりがちだが、貶す言葉は、ボクサでいえばパンチを繰り出すためにガードが下がった状態、つまり自己をさらけ出す瞬間に似ている。それを発する本人の人間性が一番よく見えるし、僕はそこに興味がある。どんな人間が世の中にいるのか、ということが、小説を書くうえでは最も重要な素材となるのだ。(P.71「2章 小説家になったあとの心構え:自分に対する批評を読む」)
この洞察力の鋭さはどうだろうか。
彼は、批判の言葉そのものの意味内容よりも、その言葉を発している「人間」そのものに興味を抱いているのである。
批判をする時、人は無防備になり、その本性をさらけ出す。
森博嗣にとって、それは飽くなき人間への興味を満たすためのサンプルであり、小説を書くための「素材」に過ぎないのである。
どのような貶す言葉であっても、それを冷静に観察し、分析し、創作の糧にしてしまう。
ここには、作品と自己の人格を明確に切り分け、客観視する科学者の目が存在する。
感情的に反応するのではなく、現象として捉える。
このメンタリティこそが、彼が大量の作品を世に送り出し続けられる理由の一つなのかもしれない。
期待に応えるのではなく裏切るマーケティング
ネット上の声を拾うことは、現代のビジネスにおいて常識となりつつある。
しかし、その活用方法においても、森博嗣は独自の哲学を持っている。
ネットによって消費者の生の声を沢山集めることができる点は、ビジネスの新しい手法として注目すべきである。それは、「声を聞いて作品に反映する」ということではあるけれど、間違えないでもらいたいのは、「期待に応えるものを作る」という意味ではない。むしろ逆である。これが僕の手法であり、常識とはかけ離れている点だろう。(P.72「2章 小説家になったあとの心構え:自分に対する批評を読む」)
多くのマーケターやクリエイターは、顧客の声を聴き、その要望に応える製品や作品を作ろうとする。
しかし、森博嗣は「逆」を行く。
読者の感想や予想を把握するのは、それを「裏切る」ためである。
読者が何を期待しているかを知れば、あえてその逆の要素を盛り込むことで、驚きや新鮮さを提供できる。
もし読者の期待通りに作ってしまえば、それは単なる予定調和であり、面白みのない作品になってしまうからだ。
確固たる自分という核を持ち、揺るがない自信があるからこそできる芸当である。
彼は、市場に迎合するのではなく、市場をコントロールしようとしているのだ。
また、彼は作家の自己マネージメントについても言及している。
小説家には、マネージャがいない。出版社はしてくれない。だから、自分で自分の作品のマネージメントをしなければならない。(P.79「2章 小説家になったあとの心構え:自己のプロモーション活動」)
これは2010年頃に書かれた言葉だが、現在においてその重要性はさらに増している。
出版社は、作家を長期的にプロモートしてくれるわけではない。
彼らがしてくれるのは、目の前の一冊を売るための宣伝だけである。
作家自身のブランド価値を高め、長期的に生き残るためには、自分自身で戦略を立て、マーケティングを行わなければならない。
SNSが普及し、個人の発信力が問われる現代において、森博嗣のこの指摘は痛いほど核心を突いている。
作家以外の強みを活かし、自分という存在をいかに演出するか。
フリーランスや個人事業主にとっても、非常に参考になる考え方である。
自信の欠如としての怒り
批判に対する森博嗣のスタンスは、さらに辛辣かつ明確な結論へと至る。
これをもう少し突き詰めると、自分の作品を人から批判されて腹が立つ人は、もう書くのをやめた方が良い、ということだ。腹が立つこと自体が、自信がない証拠だし、笑って聞き流せない思考力、想像力では、創作という行為においては明らかに能力不足だろう。(P.85「2章 小説家になったあとの心構え:自信とプライドについて」)
これほど単純明快で、かつ厳しい言葉があるだろうか。
批判に耐えられない、批判されて腹が立つというのは、自分の作品に対する論理的な自信がないからだ、と彼は断じる。
もし自分の論理が完璧であり、作品のクオリティに絶対の確信を持っていれば、的外れな批判など笑って聞き流せるはずだ、ということである。
この精神力は、単なる我慢強さとは違う。
圧倒的な思考力と想像力に裏打ちされた、強固な自負である。
この文章の裏を返せば、森博嗣自身は、自作に対して揺るぎない自信を持っており、どのような批判にも動じないだけの思考力を備えているという宣言でもある。
創作活動に限らず、仕事において他者からの評価に一喜一憂してしまう人は多い。
しかし、プロフェッショナルであるならば、自分の仕事の質を誰よりも自分自身が理解し、評価できなければならない。
他人の評価で自分の価値が揺らぐようでは、まだまだ半人前だということなのだろう。
出版業界の慣習との闘争
森博嗣は、作品の中身だけでなく、本という「商品」の製造過程においても妥協を許さない。
彼は、出版業界の理不尽な慣習や、なあなあの関係に対して、徹底的に論理で対抗してきた。
このように、僕は印刷に入った段階で本の発行を止めたことが数回ある。印刷が終わり製本された何万冊もの本をすべて廃棄させたこともある。また、あるときは、発行して書店に並んだ本をすべて回収させ、不具合を直して再発行させたことだってある。(P.103「3章 出版界の問題と将来:出版プロセスのトラブル」)
通常、著者は出版社に対して弱い立場にあることが多い。
印刷スケジュールや販売計画が決まっていれば、多少のミスや不満があっても、泣き寝入りをしてしまう著者が大半だろう。
しかし、森博嗣は違う。
商品の品質に問題があれば、たとえ数万冊の本を廃棄することになっても、発行を止める。
それは、読者という顧客に対して、不完全な商品を売るわけにはいかないという、メーカー出身者としての矜持かもしれない。
あるいは、契約と責任に対する厳格な考え方の表れかもしれない。
いずれにせよ、彼は編集者や出版社の都合よりも、商品としての完成度を優先させる。
この強気な姿勢は、多くの著者が抱えてきた不満を代弁するものであり、同時に、自分の仕事に最後まで責任を持つというプロ意識の極致である。
また、彼は広告の効果についても、自腹を切って実験を行っている。
かつては、新聞に広告を載せれば本が売れた時代もあったらしい。新聞の広告にほとんど効果がないことは、僕は実験で確かめた。(P.110「3章 出版界の問題と将来:宣伝・広告の効果」)
森博嗣は、自身の絵本『STAR EGG 星の王子さま』を刊行した際、数百万円を投じて全国紙に広告を出した。
しかし、その効果は売上で言えば1%程度、つまり費用対効果で見れば大赤字だったという。
さらに、印税を放棄して本の定価を下げてみたが、それでも売上が劇的に伸びることはなかった。
「安ければ売れる」「宣伝すれば売れる」という単純な図式は、書籍においては成立しないことを、彼は身をもって証明したのである。
重要なのは、価格や広告の量ではなく、本の内容そのものが持つ魅力、あるいは「良さそう」と思わせる雰囲気とのバランスである。
そして、継続的に作品を発表し続けることで得られる著者の信頼性こそが、最大の販促ツールなのだろう。
売れることと評価されることのパラドックス
ビジネスにおいて、売上が高い商品は、顧客満足度も高いと考えがちである。
しかし、書籍の世界、特に小説の世界においては、必ずしもそうとは限らない。
森博嗣は、自著のデータを分析し、興味深い傾向を発見した。
僕は、自著に対してデータを集計したことがある。すると、売れている本ほど、読者の採点が低くなる傾向があることに気づいた。理屈は簡単である。採点が低いからよく売れるのではなく、よく売れるほど、その作品に合わない人へも本が行き渡るから、低い評価を受ける結果にいなる。逆に、もの凄くマイナで部数の少ない本は、コアなファンだけが買うので評価が高い。(P.138「4章 創作というビジネスの展望:書評と売り上げの相関」)
これは、非常に冷静かつ論理的な分析である。
ベストセラーになればなるほど、普段本を読まない層や、そのジャンルを好まない層の目にも触れることになる。
結果として、「期待はずれだった」「意味がわからなかった」という感想が増え、平均点は下がっていく。
一方、マニアックな本は、それを求めているコアなファンしか手に取らないため、満足度は高くなる。
ある芸能人が「売れるとバカに見つかる」と言ったそうだが、まさにその通りである。
知名度が上がるということは、誤解されたり、的外れな批判を受けたりするリスクも増大することを意味する。
悪口や粗探しが増えたということは、それだけ多くの人に届いたという証拠でもあるのだ。
このメカニズムを理解していれば、ネット上の低評価にいちいち心を痛める必要がないこともわかるだろう。
森博嗣にとって、評価の低さは、むしろマスに届いたという成功の指標の一つなのかもしれない。
写真を撮るように文章を書く
小説の執筆技術に関しても、森博嗣の視点はユニークである。
彼は、文章を書く行為を、写真撮影になぞらえて説明する。
僕は写真を撮るのが好きだ。写真を撮る行為は、小説の訓練になると感じている。どこへレンズを向けるか、いつシャッタを押すか、という選択が写真の技術そのものであり、これが、文章を書く技術と基本的には同じだからだ。(P.170「5章 小説執筆のディテール:インプットとアウトプット」)
世界は情報に溢れている。
その中から、どの風景を切り取り、どの瞬間に固定するか。
写真は、三次元の世界を二次元のフレームの中に再構築する作業である。
小説も同様に、無限に広がる思考や事象の中から、特定の言葉を選び出し、文字列という記号に落とし込む作業である。
そして読者は、その記号から再び世界を脳内で構築する。
この「切り取り方」のセンスこそが、作家の個性となる。
森博嗣が写真を好むのは、それが世界を観察し、編集する訓練になるからだという発想は非常に面白い。
ただ漫然と過ごすのではなく、常に「どこを切り取るか」という意識を持って世界を見る。
その視点の鋭さが、彼の小説の乾いた、しかし鮮烈な描写に繋がっているのだろう。
また、彼はインプットとアウトプットのバランスについても言及している。
もう少し抽象的にいえば、アウトプットするほど上達する。インプットでは太るばかりで身は重くなり、動きが鈍くなるだろう。(P.170「5章 小説執筆のディテール:インプットとアウトプット」)
読書家や勉強熱心な人にありがちなのが、知識を詰め込むことだけで満足してしまう「インプット過多」の状態である。
しかし、森博嗣は言う。
インプットだけでは「太る」だけだと。
実際に手を動かし、作品を作り、世に出すこと。
アウトプットの実践の中でしか、真の上達はあり得ない。
これは、あらゆるスキル習得における真理である。
繰り返すが、とにかく自分の目で見ること。そして、自分の見たものを、自分の頭で考える(処理する)こと。創作の独創性とはこれに尽きる。(P.170「5章 小説執筆のディテール:インプットとアウトプット」)
誰かの知識や経験を借りてきただけで、それを自分のものだと錯覚してはならない。
自分で体験し、自分の頭で考え抜いたことだけが、独自の価値を持つ。
現代は情報が溢れすぎており、検索すればすぐに答えらしきものが見つかる。
だからこそ、他人の思考に支配されず、自覚的に思考することの重要性が増しているのである。
タイトルという最強の要約
森博嗣の作品において、タイトルは極めて重要な意味を持つ。
『すべてがFになる』、『スカイ・クロラ』など、彼の作品のタイトルはどれも印象的で、かつ謎めいている。
僕はタイトルが決まらない状態で小説を書き始めることはない。あとで決めれば良い、というふうには考えない。(P.189「5章 小説執筆のディテール:タイトルの重要性」)
彼は、タイトルを決めるためだけに3ヶ月から半年もの時間を費やすことがあるという。
そして、タイトルが決まれば、小説の半分以上は書けたも同然だと語る。
これは、タイトルが単なるラベルではなく、その作品の世界観、テーマ、構造すべてを凝縮した「核」であるからだ。
そのタイトルの裏側には、壮大な物語がすでに内包されている。
ビジネスにおいても、プロジェクト名やキャッチコピーは、その本質を表す重要な要素である。
中身を作ってから適当に名前をつけるのではなく、まず名前(コンセプト)を研ぎ澄ますこと。
そこからすべてが展開していくという彼の創作スタイルは、コンセプチュアルな思考の重要性を教えてくれる。
速読というナンセンス
多読家であり、知の巨人でもある森博嗣だが、読書の方法については独自のこだわりがある。
読書をする人は、多数読むことを誇りにする癖があるけれど、あれは無意味だと僕は思う。大切なのは、読んでいるときに頭に思い描くイメージの情報量であって、目がなぞった文字数ではない。速読などもまったくナンセンスだ。(P.191「5章 小説執筆のディテール:読書の姿勢」)
彼は「速読」や「多読」を無意味だと断罪する。
情報を効率的に摂取することだけを目的とするならば、速読も有効かもしれない。
しかし、小説を読む、あるいは深い思索のために本を読む場合、重要なのは文字を追うスピードではない。
その文章から喚起される「イメージの情報量」の豊かさこそが、読書の価値である。
1行の文章から、どれだけの情景、感情、思想を読み取ることができるか。
その深さこそが知性であり、教養なのだろう。
試験勉強的な情報の詰め込みと、人生を豊かにするための読書は、根本的に異なる行為なのだ。
変化を見送るという諦念と決断
本を書き上げるということは、ある時点での自分の思考を固定化することである。
しかし、人間は常に変化し、成長している。
書き始めと書き終わりでは、考えが変わっていることもあるだろう。
だから、書くことは、しかたなく変化を見送ることだ。一旦、見かけ上、止まること、といっても良い。(P.197「あとがき」)
自分の内面は常に流動的であり、変化し続けている。
しかし、作品として世に出すためには、どこかでその変化を止め、形にしなければならない。
森博嗣はそれを「しかたなく変化を見送ること」と表現する。
いつまでも修正を繰り返し、完璧を目指していては、永遠に完成しない。
変化していく自分と、固定される作品との間のギャップを受け入れ、ある種の諦念を持って「完了」させること。
これは、完璧主義に陥りがちなクリエイターにとって、非常に重要なマインドセットである。
自分の感情や思考とは別に、作品という客観物を切り離して世に放つ。
その決断の連続こそが、プロフェッショナルの仕事なのだろう。
人間への絶望と僅かな希望
最後に、森博嗣の人間観が垣間見える一節を紹介しよう。
文章を書くことは嫌いではないけれど、その中で小説の執筆が一番つまらない。自分に才能があるとはとうてい信じられないし、さらにとんでもなく酷い小説が世の中で人気を博しているのも不思議に思う。(P.198「あとがき」)
小説家が「小説の執筆が一番つまらない」と言い切る。
そして、世の中で人気のある小説を「とんでもなく酷い」と評する。
この率直すぎる言葉こそ、森博嗣のエッセイの真骨頂である。
彼は、自分自身の才能に対しても懐疑的であり、世間の評価基準に対しても冷ややかだ。
どのみち、自分は人間として生きる才能があるとは思えないし、また、僕よりも酷い人間も生きているわけで、人間は本当に不思議だ。(P.198「あとがき」)
ここには、人間という存在に対する深い絶望と、同時に興味のようなものが感じられる。
しかし、彼はこの後に続けて、それでも稀に素晴らしい才能による素晴らしい小説が存在すること、そして素晴らしい人間が存在することを挙げ、それが僅かな救いであると結んでいる。
シニカルな視点の底にある、本物への敬意。
このバランス感覚が、彼の作品に知的な奥行きを与えているのかもしれない。
総論:生き残るための冷徹な知性
『小説家という職業』を読み解くことで見えてくるのは、森博嗣という稀有な知性が、いかにして現代社会という荒野をサバイブしてきたかという記録である。
彼の言葉は、時に辛辣で、冷徹に見えるかもしれない。
しかし、それは甘えを捨て、現実を直視し、自分の頭で考え抜くことの重要性を説いているからに他ならない。
ビジネスマンであれ、学生であれ、我々はもっと戦略的に生きるべきである。
計画的に、打算的に、商売的に、建設的に、そして継続的に。
感情に流されるのではなく、メタ認知を働かせ、世の中を俯瞰して観察すること。
市場や顧客の動き、発言と行動、事実と数字を冷静に見つめ、理解すること。
そして何より、自分自身の「理想」を見失わず、そこへ向かうための具体的な施策を、淡々と実行し続けること。
森博嗣が教えてくれるのは、小説の書き方だけではない。
それは、プロフェッショナルとして自立し、この不条理な世界を楽しみながら生き抜くための、最強の「思考の方法」なのである。
今、何かに迷っている人、現状を打破したいと願っている人にとって、本書は必ずや強力な指針となるだろう。
まずは一読し、その冷たいシャワーのような論理を浴びてみてほしい。
そこから、あなたの新しい戦略が始まるはずである。
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:エッセイや随筆など
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:推理小説など読む順番も
- 森博嗣『夢の叶え方を知っていますか?』要約・感想
- 森博嗣『作家の収支』要約・感想
- 森博嗣『新版 お金の減らし方』要約・感想
- 森博嗣『自分探しと楽しさについて』要約・感想
- 森博嗣『自由をつくる 自在に生きる』要約・感想
- 森博嗣『「やりがいのある仕事」という幻想』要約・感想
- 森博嗣『孤独の価値』要約・感想
- 森博嗣『読書の価値』要約・感想
- 森博嗣『アンチ整理術』要約・感想
- 森博嗣『勉強の価値』要約・感想
- 森博嗣『諦めの価値』要約・感想
- 森博嗣『悲観する力』要約・感想
- 森博嗣『集中力はいらない』要約・感想
- 【選書】畑村洋太郎のおすすめの本・書籍12選:失敗学、数学、わかる技術
- 畑村洋太郎『失敗学のすすめ』要約・感想
- 中島義道『働くことがイヤな人のための本』要約・感想
- ジョナサン・マレシック『なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか』要約・感想
- ロバート・L・ハイルブローナー『入門経済思想史 世俗の思想家たち』要約・感想
- ジョン・ウッド『マイクロソフトでは出会えなかった天職』要約・感想
- スコット・ギャロウェイ『ニューヨーク大学人気講義 HAPPINESS』要約・感想
- ピーター・ティール『ZERO to ONE』要約・感想
- G・M・ワインバーグ『コンサルタントの秘密』要約・感想
- 中村哲『わたしは「セロ弾きのゴーシュ」』要約・感想
- 今北純一『仕事で成長したい5%の日本人へ』要約・感想
- 冲方丁『天地明察』あらすじ・感想
- 司馬遼太郎『空海の風景』あらすじ・感想
- 瀧本哲史『僕は君たちに武器を配りたい』要約・感想
- 神津朝夫『知っておきたいマルクス「資本論」』要約・感想
- 木暮太一『働き方の損益分岐点』要約・感想
- 本多静六『お金・仕事に満足し、人の信頼を得る法』要約・感想
- 竹内均『人生のヒント・仕事の知恵』要約・感想
- 藤原正彦『天才の栄光と挫折』要約・感想
- 邱永漢『生き方の原則』要約・感想
- 高橋弘樹/日経テレ東大学『なんで会社辞めたんですか?』要約・感想
- 鷲田清一『岐路の前にいる君たちに』あらすじ・感想
- 齋藤孝『座右のニーチェ』要約・感想
- 齋藤孝『日本人の闘い方』要約・感想
- 齋藤孝『最強の人生指南書』要約・感想
書籍紹介
関連書籍