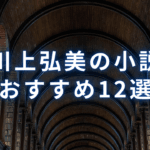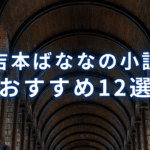- 本書は現代の情報過多社会で科学的思考を羅針盤とし、感情やデマに流されず事実を直視する重要性を冷徹に説く。
- 言葉の表面的知識が過信を生み、無知を招く罠を指摘し、現象のメカニズムを深く理解する探究心を促す。
- 人間が感情的な物語を好む弱さを批判し、再現性のある論理的プロセスこそが科学の本質だと定義する。
- 科学的思考の目標は人類の幸福であり、自分を守るツールとして活用し、人生を論理的にマネジメントする。
森博嗣の略歴・経歴
森博嗣(もり・ひろし、1957年~)
小説家、工学者。
愛知県の生まれ。東海中学校・高等学校、名古屋大学工学部建築学科を卒業。名古屋大学大学院修士課程を修了。三重大学、名古屋大学で勤務。1990年に工学博士(名古屋大学)の学位を取得。1996年に『すべてがFになる』で第1回メフィスト賞を受賞しデビュー。
『科学的とはどういう意味か』の目次
まえがき
第1章 何故、科学から逃げようとするのか
第2章 科学的というのはどういう方法か
第3章 科学的であるにはどうすれば良いのか
第4章 科学とともにあるという認識の大切さ
あとがき
『科学的とはどういう意味か』の概要・内容
2011年6月30日に第一刷が発行。幻冬舎新書。197ページ。
『科学的とはどういう意味か』の要約・感想
- 感情論では誰も救えないという冷徹な事実
- 言葉を知っているだけの「知ったかぶり」の罠
- 人間は「物語」という麻薬を求めてしまう
- 科学の定義とは「再現性」に他ならない
- 暴走するのは「科学」ではなく「経済」である
- 「思うこと」よりも「できること」を積み重ねる
- 科学の目標は、人類の幸福である
- 天才・森博嗣の仕事術と「嫌いにならない」技術
- 総論:思考の枠組みをアップデートせよ
現代社会は、あまりにもノイズが多い。
テレビをつければコメンテーターが感情的に誰かを断罪し、ネットを開けば根拠の怪しい健康法や投資話が溢れかえっている。
私たちは日々、情報の濁流の中で溺れかけている。
何が正しくて、何が間違っているのか。
何を信じれば、私たちは生き残れるのか。
そのための「羅針盤」となるのが、本書『科学的とはどういう意味か』である。
著者は、森博嗣(もり・ひろし、1957年~)。
小説家として『すべてがFになる』をはじめとする数々のベストセラーを持つ一方で、工学博士としての顔も持つ稀有な存在だ。
本書は、単なる「科学の入門書」ではない。
理系科目が苦手な人に、元素記号や物理の公式を教えるような本では断じてない。
これは、現代を生きる私たちが、不確実な未来をサバイブするために必要な「思考法」をアップデートするための本である。
これほどまでに「理性的であること」の重要性を、冷徹かつ平易に説いた書は珍しい。
特に、ビジネスの現場や日々の意思決定において、感情や空気に流されやすいと感じている人にとっては、劇薬ともなり得る一冊だ。
なぜ私たちは科学から逃げてしまうのか。
そして、科学的であることは、いかにして私たちの人生を幸福へと導くのか。
森博嗣の透徹した論理を借りて、その本質を紐解いていきたい。
感情論では誰も救えないという冷徹な事実
本書が執筆された時期には、2011年3月11日の東日本大震災があった。
未曾有の災害を前に、日本中が悲しみに暮れ、あるいは無力感に苛まれていた時期だ。
多くの言論人が、情緒的な言葉で人々の心に寄り添おうとした。
「絆」や「希望」といった言葉が連呼され、共感が求められた。
しかし、森博嗣は違った。
彼は工学者としての姿勢を崩さず、驚くほど冷静に、そして冷徹に現実を見つめていた。
以下の言葉に、その姿勢が凝縮されている。
人間にとって「気持ち」の影響力は大きい。けれど、いくら感動しても、いくら泣いても、飢えている人を救うことはできない。いくら一時の笑顔があっても、それは「解決」ではない。まして「人道支援」と「防災」は別問題である。(P.12「まえがき」)
非常に厳しい言葉に聞こえるかもしれない。
しかし、これは真理である。
被災地に必要なのは、千羽鶴や応援の歌ではなく、具体的な物資であり、インフラの復旧であり、二度と同じ悲劇を繰り返さないための物理的な対策だ。
森博嗣の科学者としての思考は、常に「課題解決」に向いている。
感情は、人間にとって大切な要素ではあるが、物理的な現象を前にしては無力だ。
涙で津波は止まらないし、祈りで放射能が消えるわけではない。
余計なノイズに惑わされず、事実だけを直視する強さ。
これこそが、科学的な態度の第一歩である。
私たちは往々にして、同情や共感を「善」とし、冷徹な分析を「悪」あるいは「冷酷」とみなす傾向がある。
だが、本当に人を救うのはどちらだろうか。
一時の感情的な連帯感か、それとも将来の被害を未然に防ぐための冷めた計算か。
森博嗣は、読者に覚悟を迫る。
科学とは、好き嫌いで選ぶアクセサリーではない。
それは、厳しい現実世界を生き抜くための必須のツールなのだ。
だから、この本に書いた意見は、「これで科学を好きになってほしい」「少しでも興味を持ってもらえれば嬉しい」ということではない。「科学から目を背けることは、貴方自身にとって不利益ですよ」そして「そういう人が多いことが、社会にとっても危険だ」ということである。(P.15「まえがき」)
科学が好きか嫌いかなど、どうでもいい。
現代社会において科学的思考を放棄することは、丸腰で戦場に出るに等しい。
それは個人の不利益に留まらず、社会全体のリスクとなる。
非科学的なデマが拡散し、誤った政策が支持され、結果として多くの人が損をする。
そうした「社会的な危険」を回避するために、私たちは科学という武器を手に取らなければならない。
言葉を知っているだけの「知ったかぶり」の罠
「科学的であること」を阻害する大きな要因の一つに、「言葉の罠」がある。
私たちは、ニュースや教科書で聞いたことがある言葉を、なんとなく理解した気になっていないだろうか。
例えば、「DNA」や「相対性理論」、あるいは「津波」という言葉。
言葉を知っていることと、その現象のメカニズムを理解していることは、全くの別物だ。
しかし、多くの人は「名称」を覚えただけで思考を停止してしまう。
言葉を覚えることで、無意識のうちに「立ち入らない」境界を作ってしまう。名称を知っていることと、それを理解していることとは同義ではない、という認識を常に持たなければならない。(P.38「何故、科学から逃げようとするのか」)
この指摘は、教育現場やビジネスの場でも頻繁に見られる現象だ。
専門用語を並べ立てて議論したつもりになっている会議。
キーワードを暗記しただけで満足してしまう学習。
言葉だけを、意味だけを覚えても、実用的な価値はゼロに等しい。
必要なのは、その背後にある構造、論理、因果関係、背景、作用を深く理解することだ。
表面的な知識は、応用が利かないばかりか、時に致命的な判断ミスを招く。
森博嗣は、津波を例に挙げて、この「理解の欠如」の恐ろしさを解説している。
数百メートル、数キロメートルという範囲で海面が持ち上がるので、その持ち上がった水量というのは、莫大な体積になる。そして、それだけの水が重力で下がる運動が伝播して岸へと押し寄せる。これが津波である。(P.41「何故、科学から逃げようとするのか」)
「津波」という言葉を知っている人は多い。
しかし、それが「波」ではなく、「海面全体の上昇」であり、想像を絶する質量の海水が移動する現象であることを、どれだけの人がイメージできていただろうか。
通常の波とはエネルギーの桁が違う。
数十センチの高さであっても、背後には数キロメートルに及ぶ海水の壁が存在する。
この物理的な原理、津波の本質的な理解があれば、堤防に対する考え方も変わってくるはずだ。
「10メートルの堤防があるから安心だ」という油断は、原理を知らないからこそ生まれる。
こういった基本的な道理を理解していれば、「10メートルの防波堤」があれば「5メートルの津波」が来ても百パーセント大丈夫だとは考えないはずである。言葉だけで知っている「過信」というものの危険性がここにある。(P.42「何故、科学から逃げようとするのか」)
道理を知らず、言葉の上っ面だけをなぞること。
それは単に教養がないというレベルの話ではなく、自らの生命を危険に晒す行為なのだ。
「過信」は、無知から生まれる。
そして、その無知は「言葉を知っている」という錯覚によって隠蔽されてしまう。
私たちが目指すべきは、百科事典的な知識の羅列ではない。
一つ一つの事象に対して、「なぜそうなるのか」「どういう仕組みなのか」を問い続ける、泥臭いまでの探究心である。
人間は「物語」という麻薬を求めてしまう
なぜ私たちは、事実よりも感情的なストーリーを好むのだろうか。
テレビのニュース番組を見れば、事象のメカニズムよりも、被害者の涙や、犯人の生い立ちといった「物語」が優先して報じられる。
それは、私たちがそれを求めているからだ。
需要があるから、供給がある。
マスメディアの偏向を批判するのは簡単だが、森博嗣はその原因を私たち自身の「弱さ」に見出している。
しかし、マスコミがそういった真の情報を伝えない理由は、大衆がそんな情報ではなく、感情的、印象的、もっといえばドラマ(物語)を求めているからにほかならない。どうして、そういったものを求めるかというと、それは、自分では考えたくないからだ。(P.56「何故、科学から逃げようとするのか」)
物語は、分かりやすい。
善と悪がいて、起承転結があり、感情移入ができる。
そこには、複雑な数式も、冷徹なデータ分析も必要ない。
ただ受け身で、感情を揺さぶられていればいい。
つまり、「考えなくて済む」のだ。
人間には本能的に、感情的で印象的なものを求めてしまう性質があるのかもしれない。
脳にとって、論理的な思考はカロリーを消費する重労働だ。
だから安易な物語に逃避する。
しかし、ここで言う「真の情報」とは、客観的に把握できるデータのことだ。
いつ、どこで、何が壊れ、何が不足しているのか。
本来、私たちが判断を下すために必要なのは、こうしたドライな事実の積み上げであるはずだ。
仕事やビジネスの現場においても、この視点は重要である。
プレゼンテーションやマーケティングでは、あえて感情や物語を利用することは有効な戦略だ。
しかし、意思決定をする側の人間が、物語に飲み込まれてはいけない。
ドラマの裏側にある骨組みを見抜く目。
それが科学的な視点である。
科学の定義とは「再現性」に他ならない
では、そもそも「科学的」とはどういうことなのか。
多くの人は、実験室で白衣を着てフラスコを振る姿や、複雑な計算式を解く姿をイメージするかもしれない。
しかし、森博嗣の定義はもっとシンプルで、かつ本質的だ。
答をごく簡単にいえば、科学とは「誰にでも再現ができるもの」である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが「科学的」という意味だ。(P.75「科学的というのはどういう方法か」)
この「誰にでも再現できる」という点が、決定的に重要である。
特定の天才にしかできないことや、偶然の奇跡は科学ではない。
条件さえ整えれば、明日誰がやっても同じ結果が出る。
それが科学だ。
観察から原理を導き出し、その手順を論理的に説明し、他者が追試できるようにする。
このプロセスの透明性と普遍性こそが、科学の信頼性の根源である。
逆に言えば、再現性のない健康法や、特定の人にしか効果のないビジネスメソッドは、科学的とは言えない。
「あの人が成功したから」といって、自分も成功するとは限らない。
そこに「再現性のあるロジック」があるかどうを見極めること。
それが、科学的な思考法を身につけるということだ。
また、森博嗣は権威主義に対しても批判的である。
ちなみに書いておくが、僕は自著で極力引用をしない。「大勢が同じことを主張しているから正しい」「有名な人が言っていることだから正しい」ということはない、と考えているからだ。(P.77「科学的というのはどういう方法か」)
確かに、森博嗣の文章には、他者の権威を借りるような引用がほとんど見られない。
「誰が言ったか」は問題ではない。
「何が語られているか」、そして「それは論理的に整合性が取れているか」だけが重要なのだ。
人数の多さや、声の大きさ、肩書きの有無で、真実は左右されない。
これは、現代のネット社会において、私たちが刻み込んでおくべき教訓だろう。
インフルエンサーが言っているから、フォロワーが多いから。
そんな理由で情報を鵜呑みにするのは、最も非科学的な態度である。
森博嗣の思考は、どこまでも個として自立しており、そして謙虚だ。
科学に対する絶対的な信頼があるからこそ、権威に頼る必要がないのだろう。
暴走するのは「科学」ではなく「経済」である
よく「科学の暴走」という表現が使われる。
核兵器や環境破壊など、科学技術の発展がもたらした負の側面を指して言われる言葉だ。
しかし、森博嗣はこの見方を否定する。
カリスマ的な指導者の発言が国民を動かしたりするようなことは、科学にはない。また、科学は、一部の特権階級にだけ、その恩恵をもたらすものでもない。科学は、経済のように暴走しないし、利潤追求にも走らない。自然環境を破壊しているのは、科学ではなく、経済ではないのか。(P.91「科学的というのはどういう方法か」)
科学そのものは、事実を明らかにする手法であり、道具である。
それは本質的に慎重で、客観的で、謙虚なものだ。
もし暴走しているように見えるなら、それは科学を使う人間の欲望、すなわち「経済」の論理が駆動しているからだ。
利潤追求、効率化、拡大再生産。
自然環境を破壊しているのは、科学技術そのものではなく、それを利益のために無制限に使おうとする経済活動である。
この視点は鋭い。
科学と経済を切り分けて考えることで、問題の所在が明らかになる。
科学は嘘をつかないが、経済は時に数字を操作し、未来を先食いする。
私たちは科学を恐れるのではなく、経済というエンジンのブレーキとして、科学的な理性を働かせるべきなのだ。
「思うこと」よりも「できること」を積み重ねる
本書の第四章では、著者の研究者としての実体験が語られる。
驚くべきは、彼のフットワークの軽さだ。
象牙の塔に閉じこもっているイメージとは裏腹に、彼は現場へ赴く。
阪神・淡路大震災のときも、2週間後に現地を歩いて調査をした。(P.166「科学とともにあるという認識の大切さ」)
震災の2週間後といえば、まだ混乱の最中だろう。
そこで現地を歩き、倒壊した建物を調査する。
原子力発電所の建設中にも見学に行き、内部構造をその目で確認しているという。
書斎で文献を読み漁るだけが研究ではない。
現実に起きた事象を、自分の目で、肌で確認し、データを集める。
この徹底したリアリズムが、彼の思考の土台にある。
災害現場で調査を行う科学者たちの姿は、被災者から見れば、時に冷淡に映るかもしれない。
人々が悲しみに暮れている横で、黙々と計測を行い、写真を撮り、メモを取る。
しかし、彼らこそが、未来の誰かを救おうとしているのだ。
そういう科学者や技術者の姿は、ときには周囲からは非人間的だと見られるかもしれない。しかし、彼らは「思うこと」ではなく、「できること」をやっているのである。「思う」だけでは誰も救えない。「できること」を実行し、そして少なくとももう二度と被害が出ないように「できる」と信じて、前進しようとしているのだ。(P.167「科学とともにあるという認識の大切さ」)
「思う」ことと「できる」ことの決定的な違い。
感情は「思う」領域にある。
同情し、怒り、悲しむ。
それは人間として自然な反応だが、それだけでは事態は好転しない。
科学者や技術者は、感情を一旦脇に置き、知恵を使って「できること」を探す。
なぜ壊れたのか、次はどうすれば壊れないか。
データを集め、仮説を立て、対策を練る。
この姿勢こそが、文明を前進させてきた。
私たちもまた、仕事や人生においてトラブルに直面したとき、この姿勢を思い出すべきだろう。
嘆いても状況は変わらない。
今、自分に「できること」は何か。
感情ではなく、論理で次の手を打つ。
冷たく見えても、それが最も誠実な態度なのだ。
科学の目標は、人類の幸福である
冷徹に見える科学的思考だが、その最終的な目的は温かい。
森博嗣は、科学の存在理由を明確に定義している。
自分の考えたものだから、利益や賞賛を独占したい、というふうには科学者は考えない。「できるだけ、大勢に使ってもらいたい」「みんなの役に立てば、それが嬉しい」というような公開性、共有性に、科学の神髄がある。社会の利益を常に優先することが科学の基本姿勢なのだ。(P.138「科学的であるにはどうすれば良いのか」)
科学知は、誰か一人のものではない。
発見された原理は、人類全体の共有財産となる。
特許などで一時的に独占されることはあっても、本質的には「公開性」と「共有性」こそが科学の魂だ。
みんなの役に立つこと。
社会の利益になること。
これが科学の基本姿勢であるならば、科学とはなんと尊いものだろうか。
科学の存在理由、科学の目標とは、人間の幸せである。したがって、もし人間を不幸にするものがあれば、それは間違った科学、つまり非科学にほかならない。そして、そうした間違いを防ぐものもまた、正しい科学以外にないのである。(P.186「科学とともにあるという認識の大切さ」)
科学の目標は「人間の幸せ」。
この言葉に救われる思いがする。
経済学も、文学も、工学も、突き詰めれば人間の幸せのためにあるはずだ。
もし、自分の人生を不幸にするような考え方に囚われているなら、それは「非科学的」な状態なのかもしれない。
自分の人生を科学的にマネジメントし、幸福という解を導き出す。
科学的思考は、そのための最強のツールとなる。
天才・森博嗣の仕事術と「嫌いにならない」技術
本書の「あとがき」には、森博嗣の人間性が垣間見えるエピソードが記されている。
彼は、中学や高校では英語が全くできなかったという。
たとえば、中学や高校では英語がまったくできなかった。国語と同様、英語の教科書に書かれている内容がつまらないからだ。(P.193「あとがき」)
ただし、これを真に受けて「森博嗣でも英語ができないんだ」と安心するのは早計だ。
彼は愛知県の名門、東海中学校・高等学校の出身である。
そこでの「できない」は、世間一般の基準とはかけ離れている。
あくまで、彼の中での相対的な評価、あるいは興味の欠如を指しているに過ぎない。
重要なのは、彼が「嫌い」という感情をどうコントロールしているかだ。
「科学を好きになる必要はない、ただ、理由もなく嫌いになるのは損ですよ」というメッセージが本書の主旨だが、「嫌いではない」は「好き」の入口である。(P.194「あとがき」)
「好き」になる必要はない。
ただ「嫌い」にならなければいい。
このハードルの低さが、新しい分野を学ぶ際のコツかもしれない。
嫌悪感さえ持たなければ、いつか必要になった時にスッと入っていける。
食わず嫌いで損をしていることは、人生に山ほどあるはずだ。
そして、森博嗣という作家の凄まじさを物語るのが、本書の執筆スピードである。
震災直後は大変忙しくなってしまい、さらに小説関係のゲラが4つも重なったりして、時間がなかなか取れなかったが、3月末になり、ようやく少し余裕ができた。本書は、そのとき、3日間、計12時間で執筆したものである。(P.197「あとがき」)
震災直後の混乱期。
工学博士として計算や相談に応じ、小説のゲラを4本抱え、その合間を縫っての執筆。
それでいて、実質3日間、計12時間でこの新書を書き上げたという。
驚異的な生産性である。
これは単なる筆の速さではない。
普段から思考が整理され、論理が構築されているからこそ、蛇口をひねるように言葉が出てくるのだろう。
彼の思考の速度と精度は、まさに長年の「科学的トレーニング」の賜物である。
また、彼の仕事の背景には、信頼できるパートナーの存在がある。
これまで幻冬舎で出した僕の本はすべて彼に担当してもらっている。それらの中でも特に僕の思い入れが強いのは、1995年から2001年までのウェブ日記を本にした5冊の日記シリーズである。今でも、自分が出版でなした仕事のうち最も価値があるのは、あれだったのではないか、と自己評価しているくらいだ。(P.195「あとがき」)
「彼」とは、編集者の志儀保博(しぎ・やすひろ、1965年~)のことだ。
幻冬舎新書を創刊した敏腕編集者であり、森博嗣との間に強固な信頼関係があることが伺える。
森博嗣が「最も価値がある」と自負する「日記シリーズ」も、この信頼関係から生まれたものなのだろう。
科学者も作家も、一人では仕事はできない。
適切なパートナーシップと、論理的な思考、そして圧倒的な集中力。
これらが組み合わさった時、プロフェッショナルな仕事が生まれるのだ。
総論:思考の枠組みをアップデートせよ
このタイトルに対する答えは、本書を読み終えた今、明確になった。
科学的とは、誰にでも再現可能な手順で、事実を積み上げること。
権威や感情に流されず、自分の頭で論理的に考えること。
そして、その目的は、社会の幸福に寄与することである。
本書を読むことで、普段いかに自分の思考が固定観念や感情に支配されているかを痛感させられる。
しかし、それは心地よい痛みだ。
凝り固まった脳の筋肉がほぐされ、視界がクリアになる感覚。
森博嗣の思考の枠組みをインストールすることは、複雑な現代社会を生き抜くための最強の武器となるだろう。
文系理系を問わず、全ての「考える人」に読んでほしい一冊である。
感情論の霧を晴らし、その先にある確かな未来を、その目で見てみないか。
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:エッセイや随筆など
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:推理小説など読む順番も
- 森博嗣『夢の叶え方を知っていますか?』要約・感想
- 森博嗣『作家の収支』要約・感想
- 森博嗣『小説家という職業』要約・感想
- 森博嗣『新版 お金の減らし方』要約・感想
- 森博嗣『創るセンス 工作の思考』要約・感想
- 森博嗣『自分探しと楽しさについて』要約・感想
- 森博嗣『自由をつくる 自在に生きる』要約・感想
- 森博嗣『「やりがいのある仕事」という幻想』要約・感想
- 森博嗣『孤独の価値』要約・感想
- 森博嗣『読書の価値』要約・感想
- 森博嗣『アンチ整理術』要約・感想
- 森博嗣『勉強の価値』要約・感想
- 森博嗣『諦めの価値』要約・感想
- 森博嗣『悲観する力』要約・感想
- 森博嗣『集中力はいらない』要約・感想
- 【選書】畑村洋太郎のおすすめの本・書籍12選:失敗学、数学、わかる技術
- 畑村洋太郎『失敗学のすすめ』要約・感想
- 中島義道『働くことがイヤな人のための本』要約・感想
- イアン・エアーズ『その数学が戦略を決める』要約・感想
- キース・デブリン/ゲーリー・ローデン『数学で犯罪を解決する』要約・感想
- ジェフリー・S・ローゼンタール『運は数学にまかせなさい』要約・感想
- ジョナサン・マレシック『なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか』要約・感想
- ロバート・L・ハイルブローナー『入門経済思想史 世俗の思想家たち』要約・感想
- ジョン・ウッド『マイクロソフトでは出会えなかった天職』要約・感想
- スコット・ギャロウェイ『ニューヨーク大学人気講義 HAPPINESS』要約・感想
- ピーター・ティール『ZERO to ONE』要約・感想
- G・M・ワインバーグ『コンサルタントの秘密』要約・感想
- 森岡毅/今西聖貴『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティング』要約・感想
- 森岡毅/今西聖貴『確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか』要約・感想
- 中村哲『わたしは「セロ弾きのゴーシュ」』要約・感想
- 冲方丁『天地明察』あらすじ・感想
- 司馬遼太郎『空海の風景』あらすじ・感想
- 瀧本哲史『僕は君たちに武器を配りたい』要約・感想
- 竹内均『人生のヒント・仕事の知恵』要約・感想
- 藤原正彦『天才の栄光と挫折』要約・感想
- 邱永漢『生き方の原則』要約・感想
- 齋藤孝『座右のニーチェ』要約・感想
- 齋藤孝『日本人の闘い方』要約・感想
- 齋藤孝『最強の人生指南書』要約・感想