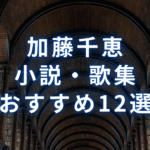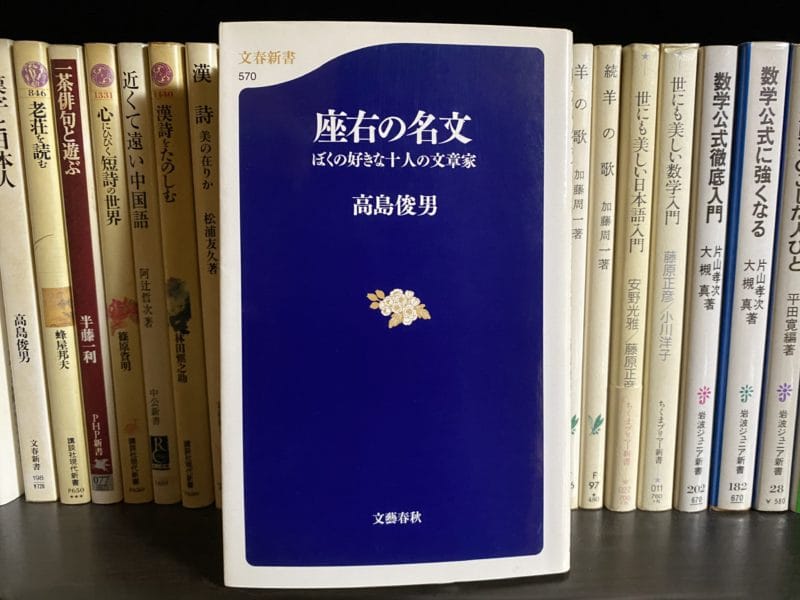
- 『座右の名文』は、明治から昭和の10人の文章家を紹介し、日本語の進化と精神史を描く本で、著者の冷静で鋭い批評が特徴。
- 寺田寅彦の安定した質の高さと幸田露伴のバラツキを指摘し、新井白石の日本語による思索の革新を強調。
- 森鷗外の超人的な多面性、内藤湖南の視点と時流の危うさ、津田左右吉の借り物思想への批判、柳田國男の文体の独自性を考察。
- 本書は歴史や人物のガイドとして機能し、現代人が古典に触れる重要性も示唆。
高島俊男の略歴・経歴
高島俊男(たかしま・としお、1937年~2021年)
中国文学者。
兵庫県相生市の出身。相生市立那波小学校、相生市立那波中学校、兵庫県立姫路東高等学校を卒業。東京大学経済学部を卒業後、銀行に勤務。
東京大学大学院人文科学研究科中国文学科を修了。専攻は中国語・中国文学。
『座右の名文』の目次
まえがき
新井白石 自分の優秀さをみずから書きのこした大秀才
本居宣長 神がかり的でもあり合理的でもあり
森鷗外 「満点パパ」と冷徹な創作家と
内藤湖南 日本初の大学出でない大学教授
夏目漱石 文明批評家としての確かな目
幸田露伴 努力の人、文章の神様
津田左右吉 戦時中、ただ一人正気を保ちつづけた
柳田國男 日本人の生活の歴史を叙述する文体
寺田寅彦 科学者の目と詩人の心
斎藤茂吉 日本語の魔術師
あとがき
『座右の名文』の概要・内容
2007年5月20日に第一刷が発行。文春新書。223ページ。
副題は「ぼくの好きな十人の文章家」。
登場人物たちは、以下の通り。
新井白石(あらい・はくせき、1657年~1725年) …江戸中期の儒学者、政治家(正徳の治を主導)。江戸(現在の東京都)の出身。
本居宣長(もとおり・のりなが、1730年~1801年) …国学者、医師。『古事記伝』の著者。伊勢国松坂(現在の三重県松阪市)の出身。
森鷗外(もり・おうがい、1862年~1922年) …小説家、陸軍軍医総監、官僚。石見国津和野(現在の島根県津和野町)の出身。
内藤湖南(ないとう・こなん、1866年~1934年) …東洋史学者、ジャーナリスト(元大阪朝日新聞論説委員)。陸奥国毛馬内(現在の秋田県鹿角市)の出身。
夏目漱石(なつめ・そうせき、1867年~1916年) …小説家、英文学者。江戸牛込(現在の東京都新宿区)の出身。
幸田露伴(こうだ・ろはん、1867年~1947年) …小説家、随筆家、考証家。江戸下谷(現在の東京都台東区)の出身。
津田左右吉(つだ・そうきち、1873年~1961年) …歴史学者、思想史家(早稲田大学教授)。岐阜県美濃加茂市の出身。
柳田國男(やなぎた・くにお、1875年~1962年) …民俗学者、官僚(貴族院書記官長など)。兵庫県神崎郡(現在の福崎町)の出身。
寺田寅彦(てらだ・とらひこ、1878年~1935年) …物理学者、随筆家、俳人。東京(現在の東京都千代田区)の生まれ、高知県高知市の育ち。
斎藤茂吉(さいとう・もきち、1882年~1953年) …精神科医、歌人。山形県南村山郡(現在の山形県上山市)の出身。
『座右の名文』の要約・感想
- 批評の切れ味:寺田寅彦と幸田露伴
- 新井白石の革命:母語で語るということ
- 森鷗外の二面性:鉄の意志と父の愛
- 内藤湖南の視座:冷徹なリアリズムの危うさ
- 幸田露伴を囲む人々:口伝される巨人の実像
- 津田左右吉の孤独な闘い:疑うことの力
- 柳田國男の文体:現実と幻想の境界線
- 総論:『座右の名文』を読むということ
高島俊男(たかしま・としお、1937年~2021年)による『座右の名文』。
著者の高島俊男は、中国文学者として深遠な知識を有しつつ、エッセイストとしても鋭い切れ味を見せる稀有な存在である。
本書は、彼が愛してやまない十人の文章家を取り上げ、その魅力を縦横無尽に語り尽くした一冊だ。
2007年に文春新書から刊行された本書は、単なる名文のアンソロジーではない。
それは、明治から昭和にかけての日本の知性が、どのように日本語をアップデートし、思想を構築してきたかを描く、壮大な精神史でもある。
本記事では、この書籍を通して、日本語の深淵とその可能性について考察していく。
批評の切れ味:寺田寅彦と幸田露伴
本書の冒頭、まえがきからいきなり高島俊男の批評眼が光る。
多くの評論家が、巨匠と呼ばれる作家に対しては歯の浮くような賛辞を並べがちな中で、彼は極めて冷静に、そして冷徹に対象を見つめている。
その対象とは、科学者であり随筆家でもあった寺田寅彦(てらだ・とらひこ、1878年~1935年)と、明治の文豪である幸田露伴(こうだ・ろはん、1867年~1947年)である。
一番ツブがそろっていて、まず駄作というもののないのが寺田寅彦である。一番駄作の多いのが露伴である。(P.8「まえがき」)
ここまではっきりと断言しているのが面白い。
寺田寅彦はまとまっていて、幸田露伴はバラツキがあるということか。
幸田露伴を批判している文章など、これまであまり目にした記憶がないため、この指摘は非常に新鮮であった。
一般的に「文章の神様」とまで崇められる露伴に対して、「駄作が多い」と言い切れるのは、著者が膨大な量の文献を読み込み、自身の審美眼に絶対的な自信を持っている証拠であろう。
著者のこの評価を目にして、改めて寺田寅彦の「ツブのそろった」文章を読み返してみたくなった。
科学者特有の観察眼と、詩人の感性が融合した彼の随筆は、確かにムラがなく、常に一定のクオリティを保っているのかもしれない。
一方で、露伴の「駄作」とは何を指すのか。
それはおそらく、彼の博覧強記が過ぎて、読者を置き去りにするような難解さや、衒学的な部分を指しているのかもしれない。
しかし、その「駄作」の山の中に、とてつもない傑作が埋もれているのが露伴の魅力とも言える。
このまえがきだけで、読者は高島俊男というガイド役が、決して権威に媚びず、自身の感覚を信じて案内してくれることを確信できるのだ。
新井白石の革命:母語で語るということ
次に著者が取り上げるのは、江戸中期の儒学者であり政治家でもあった新井白石(あらい・はくせき、1657年~1725年)である。
歴史の教科書では「正徳の治」を行った政治家として知られるが、本書では彼の「文章家」としての側面にスポットライトが当てられている。
新井白石は、学者でありながら日本のことを日本語でかいたという、まことに画期的なことをした人物なのだ。(P.32「新井白石」)
現代の私たちからすれば、「日本のことを日本語で書く」というのはごく当たり前のことのように思える。
しかし、当時、江戸の中期において、学問といえば中国の学問のことであり、公的な文章や思想書は中国語(漢文)で書くというのが常識であった。
この歴史的な前提、時代背景が分かっていないと、白石の成し遂げたことのセンセーショナルさが理解できない。
これは西洋におけるラテン語と俗語(各国語)の関係に似ている。
長らくラテン語が知識階級の共通言語であったヨーロッパで、ダンテ・アリギエーリ(Dante Alighieri、1265年~1321年)がトスカーナ方言で『神曲』を書いたような衝撃に近いかもしれない。
白石は、漢文という借り物の言葉ではなく、自らの母語である日本語を用いて、論理的かつ格調高い文章を構築しようと試みた先駆者であった。
著者は、白石の自己プロデュース能力の高さについても言及している。
彼は自分の業績や考えを、後世にいかに伝えるかという点において非常に意識的であった。
この点は、平安時代の僧侶、空海(くうかい、774年~835年)に通じるものがあるかもしれない。
もちろん、空海より規模は小さく、影響力も限定的であり、晩年は失脚して不遇をかこった点は悲しいものがある。
最後は嫌われて孤独だったという話もあり、その孤高の精神が、より一層彼の日本語の文章を研ぎ澄ませたのかもしれない。
彼が切り開いた「日本語による思索」の道は、後の国学者たち、そして明治の言文一致運動へと繋がる重要なマイルストーンであったことは間違いない。
森鷗外の二面性:鉄の意志と父の愛
明治の文豪、森鷗外(もり・おうがい、1862年~1922年)についての章は、彼の人間的な魅力が溢れている。
陸軍軍医総監という軍のトップに登り詰め、同時に小説家として文学史に残る傑作を次々と発表した鷗外。
その超人ぶりは有名だが、本書では彼の家庭人としての顔に注目している。
鷗外の子どもたちの書いたものを読んでおもしろいのは、四人が四人とも「自分がいちばんかわいがられた」と思っていることだ。(P.62「森鷗外」)
これは驚くべきことである。
全員がそれぞれにそう思わせる愛情深い森鷗外、子煩悩な森鷗外。
本当に凄いな。
仕事では軍医として組織の頂点に立ち、激務をこなしながら、小説・翻訳でも文豪として第一線で活躍し、後輩作家の面倒も見つつ、家庭・子育てについても、これほど素晴らしい対応をしていたとは。
彼は一体いつ寝ていたのだろうか。
睡眠時間はあったのだろうか。
凡人なら寝ないで24時間対応しても、これだけのタスクをこなしつつ、子供たちに「自分が一番愛されている」と感じさせるほどの情緒的なケアを行うことは無理なような気がする。
体力も精神力も、そして知力も、全てにおいて桁違いの傑物ということか。
鷗外の文章が持つ、あの硬質で無駄のない、しかしどこか温かみを感じさせる文体は、こうした強靭な精神と深い愛情のバランスの上に成り立っていたのかもしれない。
そして、鷗外の生き方そのものに通じるような、興味深い引用がある。
徒然草に「狂人の真似とて大路を走らば即ち狂人なり」ということばがある。芝居といっても徹底的にまねをすればそれが本物になってしまう、という意味だ。(P.72「森鷗外」)
これは『徒然草』の著者、兼好法師(けんこう・ほうし、1283年頃~1352年以降)の言葉を引いたものだが、鷗外という人物の本質を突いているようで面白い。
この言葉は、良くも悪くも使える教訓を含んでいる。
上手くプラスに活用したいところである。
もちろん、それは簡単なことではない。
しかし、これは具体的で行動に移しやすい指針であり、現実化しやすい成功法則の一つかもしれない。
鷗外自身、軍人としての自分、作家としての自分、父としての自分を、それぞれの場面で完璧に「演じ切る」ことで、あれほどの業績を残したのではないだろうか。
内藤湖南の視座:冷徹なリアリズムの危うさ
歴史学者でありジャーナリストでもあった内藤湖南(ないとう・こなん、1866年~1934年)の章では、彼の透徹した中国観と、それが当時の日本に与えた影響について分析されている。
湖南は、実証的な東洋史学(支那学)を確立した巨人の一人であるが、その視点は常にドライで現実的であった。
<中略>内藤湖南の、日本は東京文化圏の一部なんだから、その中心である支那へ乗りだして行ってもさしつかえない、という「きわどい論法」が、日本の膨張思想に結びついたことは否定できない。(P.88「内藤湖南」)
内藤湖南の中国をフラットに見る姿勢。
特に大げさに敬うことなく、科学的に考えて、オカシイと思った箇所は批判するという態度は、学問的には非常に誠実なものであったはずだ。
彼は中国の歴史や文化を深く愛していたが、それは盲目的な崇拝ではなく、対象を突き放して観察する解剖学者のような愛であった。
しかし、そこから派生した「文化の中心が移動する」という考え方が、当時の日本の大陸進出を正当化する時流と重なってしまい、結果として危うい思想の後押しになった感があるという指摘は鋭い。
これは、優れた知性が必ずしも良き政治的結果をもたらすとは限らないという、歴史の皮肉であり、勉強にもなる視点だ。
また、湖南の文章家としての才能、特に講演の名手としての側面についても触れられている。
ほかにも多くの講演をした人はあまたあるが、ほぼ百年たったいまでもみずみずしく立派で、じゅうぶん読むに値する講演をしたのは、湖南と漱石っくらいのものなんじゃないかしら。(P.89「内藤湖南」)
1907年~1916年まで朝日新聞に入社していた夏目漱石(なつめ・そうせき、1867年~1916年)は、全国で数多くの講演を実施した。
『私の個人主義』などは今でも広く読まれている。
同様に内藤湖南も、各地で講演を実施し、その速記が本になっている。
この二人以外にも多くの知識人が講演を行ったが、現在でも読むに値して、かつ文庫などで簡単に手に入るのは、確かにこの二人くらいかもしれない。
話言葉を文字に起こした時に、それが一級の読み物として成立するためには、論理の構成力と、言葉選びのセンス、そして何よりも語り手の人格的な魅力が不可欠である。
湖南の講演録を読むと、彼がいかに博識であり、かつ聴衆を飽きさせない語り口を持っていたかがよく分かる。
幸田露伴を囲む人々:口伝される巨人の実像
冒頭で「駄作が多い」と評された幸田露伴だが、著者の露伴への関心は尽きない。
特に、露伴の周囲にいた人々が書き残した記録を通して、露伴という人間の実像に迫ろうとするアプローチが興味深い。
一人は小林勇で『蝸牛庵訪問記』という本、もとは岩波書店から出て、いまは講談社の文芸文庫に入っている。
もう一人は、内田誠という人が『落穂抄―露伴先生に聞いた話』というのを書いた。(P.117「幸田露伴」)
露伴の話をまとめたこの二人。
小林勇(こばやし・いさむ、1903年~1981年)は編集者として、内田誠(うちだ・まこと、1893年~1955年)は随筆家として、それぞれの視点から露伴の言葉を記録している。
ただ、塩谷賛(しおたに・さん、1916年~1977年)という人物もいるが、彼はあまりに露伴に心酔しすぎて、もはや幸田露伴の分身みたいな人物になってしまっているから除外しているとのこと。
この選別の基準も、著者らしくて面白い。
幸田露伴の話を、まるで神託のようにありがたく聞いていた人たちが当時はいかに多かったか。
露伴の家、通称「蝸牛庵(かぎゅうあん)」には、多くの文化人が集い、彼の該博な知識と独特の人生哲学に耳を傾けたという。
文章だけでなく、その存在そのものが一つの巨大な磁場となっていた露伴。
彼の肉声は失われてしまったが、弟子たちの記録を通して、その圧倒的な存在感の一端に触れることができるのは幸運なことである。
津田左右吉の孤独な闘い:疑うことの力
歴史学者、津田左右吉(つだ・そうきち、1873年~1961年)の章は、学問における「疑うこと」の重要性を教えてくれる。
彼は『古事記』や『日本書紀』を批判的に研究し、戦時中には著書が発禁処分になるなどの弾圧を受けたが、それでも自らの学問的良心を曲げなかった。
ぼくが生涯最大の影響をうけた本、『支那思想と日本』にもこの思想がつらぬかれている。(P.143「津田左右吉」)
著者が「生涯最大の影響を受けた」とまで語るこの思想。
それは、「支那人の思想は支那人の生活から生れてきたものであって、生活基盤がちがう日本人にはなんのゆかりものないものである、と左右吉は考えた」というものだ。
いわれてみれば、確かにその通りである。
思想や哲学というものは、その土地の気候、風土、生活習慣と不可分のものであるはずだ。
しかし当時は、いや現在においてさえ、私たちは中国からの思想、あるいは西洋からの思想を、疑うこともなくありがたく受け取ってしまいがちだ。
儒教にしろ、朱子学にしろ、陽明学にしろ、それらを「普遍的な真理」として無批判に受容していた当時の知的風土の中で、津田左右吉の考え方は、非常にユニークで奇抜、かつ本質を突いたものであった。
この「借り物の思想」への違和感こそが、津田史学の原点であったのだ。
また、津田左右吉の学歴に関する記述からは、当時のアカデミズムの階層構造が見えてくる。
東京大学及び帝国大学(特に東京大学)は洋学校だから、授業は西洋語でおこなわれていた。英語やドイツ語ができなことには、教室へで出たって先生のしゃべっていることがわからない。そこに目をつけたのが東京専門学校だった。左右吉が入ったのは「邦語政治科」という学科。邦語、とわざわざうたっているところが、いかにも早稲田らしい。(P.146「津田左右吉」)
ここでは東京大学出身の著者から、早稲田大学(当時の東京専門学校)への下に見るような視線、思考が読み取れるのが興味深い。
商売上手な早稲田という風に書かれている部分だ。
当時は、西洋語、つまり英語、ドイツ語、フランス語で授業が行なわれるのが「最高学府」の証であった。
そこで、あえて日本語だけで授業を行なったのが現在の早稲田大学、当時の東京専門学校である。
さらに、理科系の医科や工科もない。
実験室も高価な器具も不要で、極端な話、講師の口と黒板さえあれば授業ができるから、とも書かれている。
確かにそうではあるが、ここは国立と私立の成り立ちの違い、予算の出どころの違いといった方が分かりやすいかもしれない。
しかし、結果として、日本語で政治や経済、法律を学ぶ道を開いた早稲田の功績は大きい。
「正規の教育」とは、この時代、欧米の言語をつかって欧米の学問を学ぶことをさす。(P.148「津田左右吉」)
津田左右吉は、才能もあり勉強も驚くほどしているが、この定義における「正規の教育」を受けていないことになる。
そのため、ヨーロッパへのあこがれ、コンプレックスが人一倍強かったのでは、と著者は推測している。
なるほど、当時の「正規の教育」のハードルの高さ、そして言語の壁がいかに厚かったかを感じさせるエピソードだ。
このコンプレックスこそが、逆に彼を日本や中国の古典文献の精読へと向かわせ、独自の学問体系を築き上げる原動力になったのかもしれない。
柳田國男の文体:現実と幻想の境界線
民俗学の父、柳田國男(やなぎた・くにお、1875年~1962年)の章では、彼の代表作『遠野物語』の文学的価値について言及されている。
柳田國男は官僚出身でありながら、日本全国を歩き、名もなき人々の伝承を記録し続けた。
彼の文章は、学術論文というよりは、一種の散文詩のような趣がある。
現実と非現実との蝶番たる、まわる炭取。『遠野物語』の一番すごみのあるところを見つけだした三島由紀夫もえらいし、われわれ文学青年もそれを読んで大きな衝撃をうけたのだった。(P.161「柳田國男」)
『遠野物語』の中に登場する、怪異が起きる直前の描写、例えば「炭取(すみとり)がひとりでくるくると回る」といったシーン。
三島由紀夫(みしま・ゆきお、1925年~1970年)は、この「まわる炭取」の部分にこそ、近代小説が失ってしまった「小説の核」を発見した。
三島は自身の評論「小説とは何か」でこの点に言及している。
確かにこれは凄い指摘である。
幽霊が出た、妖怪が出た、という結果そのものよりも、日常の風景がふとした瞬間に異界へと、つながる、その「蝶番(ちょうつがい)」のような瞬間の描写。
そこが物語の肝ということである。
柳田國男の文章が持つ、ある種の不気味さと美しさは、彼が単なる記録者にとどまらず、優れた文学的感性を持っていたことを証明している。
それは、借り物の漢文脈でもなく、翻訳調の欧文脈でもない、日本人の土着の感覚に根ざした、新しい言葉の獲得であった。
総論:『座右の名文』を読むということ
本書『座右の名文』を通して、さまざまな学者、作家たちの思考の軌跡と、その文章の妙味を知ることができたのは大きな収穫であった。
ただ、タイトルが『座右の名文』となっているが、内容は単なる名文の紹介にとどまらず、人物評伝や文学史的考察の色合いが濃い。
その意味では、タイトルと内容が少し合っていないと感じる読者もいるかもしれない。
しかし、著者の文章そのものが、口述筆記をベースに編集されたものであるため、非常に口語的であり、リズムが良く、読みやすい。
本書は、ある意味で「読書のためのブックガイド」としても機能する。
ここで紹介された十人の著作を、今度は原典で味わってみるのも良いだろう。
気になった人物を、さらに掘り下げていってみてはいかがだろうか。
現代の私たちは、SNSなどで短文でのコミュニケーションに慣れきってしまっている。
しかし、時にはこうした明治・大正・昭和の巨人たちの、骨太で、論理的で、かつ情感豊かな文章に触れることで、自分自身の言語感覚のメンテナンスをする必要があるだろう。
『座右の名文』は、そのための最良の入り口となる一冊である。
- 加賀乙彦『鷗外と茂吉』あらすじ・感想
- 真山知幸『文豪が愛した文豪』要約・感想
- 進士素丸『文豪どうかしてる逸話集』要約・感想
- 永田龍太郎『散華抄』あらすじ・感想
- 森功『鬼才 伝説の編集人 齋藤十一』あらすじ・感想
- 小泉信三『わが文芸談』要約・感想
- 室生犀星『我が愛する詩人の伝記』あらすじ・感想
- 茨木のり子『詩のこころを読む』あらすじ・感想
- 猪瀬直樹『こころの王国』あらすじ・感想
- 猪瀬直樹『ピカレスク』あらすじ・感想
- 猪瀬直樹『マガジン青春譜』あらすじ・感想
- 出口汪『超訳 鷗外の知恵』要約・感想
- 三輪裕範『超訳 努力論 幸田露伴』要約・感想
- 斎藤兆史『努力論』要約・感想
- 宮沢和樹『わたしの宮沢賢治 祖父・清六と「賢治さん」』要約・感想
- 宮沢清六『兄のトランク』要約・感想
- 草野心平『宮沢賢治覚書』要約・感想
- 中原フク・述/村上護・編『私の上に降る雪は』要約・感想、家系・兄弟
- 中原呉郎『海の旅路 中也・山頭火のこと他』要約・感想、家系・兄弟
- 中原思郎『兄中原中也と祖先たち』要約・感想、家系・兄弟
書籍紹介
関連書籍
関連スポット
本居宣長記念館
三重県松阪市殿町にある本居宣長の記念館。本居宣長の生まれ育った場所。
公式サイト:本居宣長記念館
森鴎外記念館(観潮楼跡・東京都)
東京都文京区千駄木にある森鴎外の記念館。森鴎外が晩年を過ごした旧宅・観潮楼の跡地。
公式サイト:森鴎外記念館
森鷗外記念館(島根県)
島根県鹿足郡津和野町にある森鴎外の記念館。森鴎外の生まれ育った場所であり、森鴎外旧宅もある。
公式サイト:森鷗外記念館
漱石山房記念館
東京都新宿区早稲田南町にある夏目漱石を記念した博物館。夏目漱石は新宿の生まれ育ちで、1916年に亡くなるまでの9年間を現在の新宿区早稲田南町で過ごした。
公式サイト:漱石山房記念館
柳田國男・松岡家顕彰会記念館
柳田國男・松岡家顕彰会記念館は、柳田国男をはじめとする松岡家五兄弟の出身地にある兵庫県神崎郡福崎町の文化施設。
公式サイト:柳田國男・松岡家顕彰会記念館
斎藤茂吉記念館
山形県上山市北町にある斎藤茂吉の記念館。斎藤茂吉の生まれ育った場所。
公式サイト:斎藤茂吉記念館