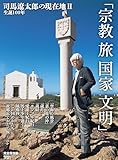司馬遼太郎の略歴
司馬遼太郎(しば・りょうたろう、1923年~1996年)
小説家、ノンフィクション作家、評論家。
大阪府大阪市の生まれ。大阪外国語大学蒙古学科を卒業。
産経新聞社の記者として在職中の1960年に『梟の城』で第42回直木賞を受賞。本名は、福田定一(ふくだ・ていいち)。
『新聞記者 司馬遼太郎』の目次
序章
第1章 廃墟の町から
第2章 古都の片隅で
第3章 雌伏の支局記者
第4章 文化部の机にて
第5章 作家への助走
第6章 海外での取材
第7章 交遊、その流儀
第8章 新聞記者を語る
あとがきにかえて 辺境の目 司馬文学の原郷 石井英夫
記者時代のコラム
司馬遼太郎氏の略歴
文春文庫版へのあとがき 皿木喜久
概要
2013年6月10日に第一刷が発行。文春文庫。299ページ。
司馬遼太郎の新聞記者の側面に焦点を当てたノンフィクション作品。司馬遼太郎は1948年~1961年まで産経新聞社に勤務した。
2000年2月に扶桑社(産経新聞ニュースサービス発行)から単行本が刊行。2001年11月に扶桑社文庫から文庫版が刊行。
上記のような経緯がある。
産経新聞の文化部記者時代の15本のコラムが掲載されいているのも注目のポイント。
「あとがきにかえて 辺境の目 司馬文学の原郷」は、コラムニストで、産経新聞社に勤務経験のある石井英夫(いしい・ひでお、1933年~)。
神奈川県横須賀市の生まれ。神奈川県立横須賀高等学校、早稲田大学第一政治経済学部を卒業。1955年~2008年まで産経新聞社に勤務。司馬遼太郎と産経新聞社での勤務の時期が1955年~1961年まで重なる。
「文春文庫版へのあとがき」は、産経新聞社に勤務経験のある皿木喜久(さらき・よしひさ、1947年~)。
鹿児島県の生まれ。京都大学文学部を卒業。1971年~2015年まで産経新聞社に勤務。
感想
私は、そこまで司馬遼太郎の良い読者ではないかも。
しっかりと読んだ作品は『空海の風景』くらいである。ただ、司馬遼太郎記念館には実際に訪問したことはある。
この書籍は、何かで見かけて興味を持ったので購入。新聞記者としての司馬遼太郎を知りたいと思ったから。
正確には、本名の福田定一についてである。ただ、作家・司馬遼太郎とも切り離せないものである。
なかなか面白かった。というか、とても面白かった。
ただ、終わり方が中途半端というか、あれ、これで、終わりなの、という幕切れ。
加えて、新聞記者時代の司馬遼太郎のコラムも掲載されているが、何となくイマイチだったかも。
当時の一般読者に向けて書かれているからか、ちょっと時代を感じる文章。文体か。
新聞の一部分のコラムだから、サラッと読めるものが良いのかも。かなり、ポップというか、サラリとした感じ。
司馬遼太郎ファンは楽しめるのかもしれない。
あとは、産経新聞社の記者たち、取材班たちが執筆しているので、新聞記者の持ち上げ方が、少々鼻に付いた感じは否めない。
その辺りは、もっと抑えてくれた方が、冷静なというか、落ち着いた空気感を出せたのかも。
まぁ、新聞記者の矜持というか、そういうのが出ちゃってしまうのも仕方がないが。
近藤紘一(こんどう・こういち、1940年~1986年)にも触れられていたのは、興味深い発見であった。
近藤紘一は、新聞記者でノンフィクション作家。東京都の生まれ。神奈川県の育ち。神奈川県立湘南高等学校を卒業。早稲田大学第一文学部仏文科を首席で卒業。現在の産経新聞であるサンケイ新聞に入社。海外特派員として勤務。
1979年に『サイゴンから来た妻と娘』で大宅壮一ノンフィクション賞を、1984年に『仏陀を買う』で中央公論新人賞を受賞している。
加えて、司馬遼太郎が奥さんへのプロポーズをする場面の記述は笑った。
以下、引用などをしながら紹介。
文化部に在籍していたころの司馬は、「一日に五時間の読書を日課にしている」と周囲にもらしている。百科事典を毎日一ページずつひきちぎって読み、一日で頭に入れてしまった、というエピソードも伝えられている。(P.122「第4章 文化部の机にて」)
仕事をしながら、1日に5時間の読書。
いったい、睡眠時間はどれくらいだったのだろうか。ショートスリーパーということか。
あとは、確かかなりの速読もできる人物だったという話もあったような。
人を待っている数分か、十数分で薄い文庫本を読み終えてしまったとか。
司馬遼太郎は、同人雑誌というものが苦手だった。いや、はっきりと嫌いだったといっていい。文学青年が徒党を組んで、ああだこうだと文学を語るなんていうのは性に合わない。なにしろ、小説を書こうと志したものの、少年のころから、好きな作家というもの、熟読した小説もなかった。(P.151「第5章 作家への助走」)
まずは、同人雑誌や徒党を組む文学青年が苦手だったという話。
なるほど。確かに新聞記者といった現実的な文章を書く人間からすると、ちょっと種類の異なるかもしれない。
さらに、好きな作家や熟読した小説も無かったという話。
そんな感じだったのか。むしろ、そういった感じだからこそ、自分で書こうと思ったのか。
結構、新鮮な驚きのある部分である。
ベトナムには、司馬遼太郎、みどり夫妻に加えて、サイゴン特派員を務めたことがある友田錫、大阪本社文化部の中野喬二、写真部OBの伊藤久美子の三人が同行した。サイゴンでは特派員の近藤紘一が出迎えた。(P.178「第6章 海外での取材」)
ここで、近藤紘一も登場している。
サイゴンは旧称であり、現在のホーチミン市。ベトナム社会主義共和国の南部に位置した大都市であり、東南アジアでも有数の世界都市。
1973年2月の取材旅行の時のことである。
この時が司馬遼太郎と近藤紘一の初めての出会いだったとか。
どこまで仲良くなったのかは不明ではあるが、近藤紘一が亡くなった際には、司馬遼太郎は、異例の長時間にわたる弔事を寄せたという記述も。
「第8章 新聞記者を語る」の225ページには、その弔事の一節も掲載されている。
「あとがきにかえて 辺境の目 司馬文学の原郷」で石井英夫は、司馬遼太郎の『街道をゆく』を、天台宗の僧・円仁(えんにん、794年~864年)の『入唐求法巡礼行記』と重ね合わせている。
さらに博物学者・南方熊楠(みなかた・くまぐす、1867年~1941年)の引き合いに出す記述も。
最後まで非常に楽しめる内容になっている。
司馬遼太郎のファンはもちろん、司馬遼太郎に興味のある人には非常にオススメのノンフィクション作品である。
書籍紹介
関連書籍
関連スポット
司馬遼太郎記念館
司馬遼太郎記念館は、大阪府東大阪市にある司馬遼太郎の自宅敷地を利用した文化施設。
実際に訪問したことがある。評判通り、高さ11メートルの書架は壮観だった。
公式サイト:司馬遼太郎記念館