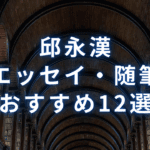- 森博嗣は、作家の収入源として原稿料や印税、その他について具体的に解説。
- 驚異的な執筆スピードは時給10万円相当を生み、プロとしての効率と戦略を強調。
- 仕事哲学として、締切厳守、多作を提唱。執筆を冷静に「仕事」として扱う。
- 成功の鍵は「自己矛盾」の内包。19年で15億円の軌跡を示し、多作と合理性の助言。
森博嗣の略歴・経歴
森博嗣(もり・ひろし、1957年~)
小説家、工学者。
愛知県の生まれ。東海中学校・高等学校、名古屋大学工学部建築学科を卒業。名古屋大学大学院修士課程を修了。三重大学、名古屋大学で勤務。1990年に工学博士(名古屋大学)の学位を取得。1996年に『すべてがFになる』で第1回メフィスト賞を受賞しデビュー。
『作家の収支』の目次
まえがき
第1章 原稿料と印税
第2章 その他の雑収入
第3章 作家の支出
第4章 これからの出版
あとがき
『作家の収支』の概要・内容
2015年11月30日に第一刷が発行。幻冬舎新書。204ページ。
『作家の収支』の要約・感想
- 作家の収入源:原稿料と印税の仕組み
- 時給10万円?驚異的な執筆スピードの秘密
- 本の価格と印税率の現実
- 印税だけではない多様な収入源
- プロとして仕事を獲得し続けるための戦略
- デジタル化とグローバル化の波
- サイン会は誰のため?ドライな分析眼
- メディアミックスがもたらす利益
- 作家は生き残れるか?未来への提言
- スランプとは無縁の執筆哲学
- 19年で15億円。数字が語る成功の軌跡
- まとめ:成功の条件は「自己矛盾」にある
作家という職業に、どのようなイメージを持っているだろうか。締め切りに追われながらも、創造性豊かな世界を紡ぎ出す自由な仕事。
あるいは、ごく一握りの成功者だけが生き残れる、才能だけがものをいう厳しい世界。
その華やかさと厳しさの裏側、特に「お金」に関する現実は、厚いベールに包まれていることが多い。
今回紹介する一冊は、そんな作家の懐事情を、人気ミステリィ作家である森博嗣(もり・ひろし、1957年~)が自ら赤裸々に綴った『作家の収支』である。
本書は単なる暴露本ではない。
元大学工学部の准教授という異色の経歴を持つ彼ならではの、極めて論理的でドライな分析眼が輝く。
作家という職業、ひいては現代社会における「仕事」と「お金」の本質を浮き彫りにする、優れたビジネス書であり、人生論でもあるのだ。
クリエイティブな仕事は、情熱や感性といった言葉で語られがちである。
しかし、森博嗣はそれを「ビジネス」として冷徹に分析し、具体的な数字をもって解体していく。
その姿勢は、ともすれば夢のない話に聞こえるかもしれない。
だが、その先に見えてくるのは、感情論を排したプロフェッショナルとしての確固たる矜持と、極めて合理的な生存戦略である。
この記事では、『作家の収支』の内容を深く紐解きながら、作家という仕事の具体的な収入と支出、そして森博嗣の独特な仕事哲学に迫ってみたい。
クリエイティブな仕事に興味がある人はもちろん、自らの仕事の価値について深く考えたいと願うすべての人にとって、必ずや新たな発見と刺激が得られるはずだ。
作家の収入源:原稿料と印税の仕組み
作家の収入の二大支柱は、原稿料と印税である。
これらが具体的にどのくらいの金額なのか、多くの人が最も知りたい部分だろう。
森博嗣は、自身の経験に基づいた具体的な数字を挙げて、その仕組みを明快に解説している。
まず、書籍になる前の段階、つまり雑誌などに小説を掲載する際の「原稿料」について見てみよう。
小説雑誌などでは原稿用紙1枚に対して、4000円~6000円の原稿料がもらえる。たとえば、50枚の短編なり連載小説を書けば、20万円~30万円が支払われるわけで、毎月これがコンスタントにかければ、生活には充分な額になるだろう。(P.26「第1章 原稿料と印税」)
400字詰めの原稿用紙1枚あたり、数千円というのが一つの目安となる。
ただし、文字数としては改行や空白行などにより、300字くらいになるのが実情のようだ。
月刊誌で100枚の連載を持てば、それだけで40万円から60万円の収入になる計算だ。
これだけであれば、安定した職業と何ら変わりないように思える。
さらに、影響力の大きいメディア、例えば全国紙の連載小説ともなれば、その額は桁違いに跳ね上がる。
新聞の連載小説などは(地方紙、全国紙でさまざまだが)、1回分が5万円ほどで、これが毎日だから(休みの日があるのが一般的だが)、1年間連載をすれば、この連載だけで1800万円の年収になる。(P.27「第1章 原稿料と印税」)
これは森博嗣自身が経験したわけではないものの、実際にあったオファーに基づくかなり正確な数字だという。
毎日掲載される新聞という媒体の力を考えれば、この金額も納得がいく。
一つの連載だけで、多くのビジネスマンが一生かかって稼ぐ金額に近い額を稼ぎ出す可能性を秘めているのだ。
作家という職業の持つポテンシャルの高さがうかがえる。
時給10万円?驚異的な執筆スピードの秘密
このような高額な収入を得るためには、当然ながら相応の労働、すなわち執筆が必要となる。
では、作家の仕事を時給に換算すると、一体いくらになるのだろうか。
ここで森博嗣は、自身の驚異的な執筆能力について、工学者らしい定量的な分析を交えて言及する。
僕は、キーボードを叩いて文章を書く。1時間当りに換算すると6000文字を出力できる。(P.27「第1章 原稿料と印税」)
1時間で6000文字。
一般的なビジネス文書の作成スピードを遥かに凌駕するこの速度は、彼の特異な執筆スタイルに起因する。
頭の中に流れ続ける映像を、ただひたすら文字に書き起こしていく。
映像の再生速度を任意にコントロールできないため、このスピードで書き続けるしかないのだそうだ。
この驚異的なアウトプットを原稿料に換算すると、衝撃的な時給が算出される。
6000文字というのは、原稿用紙にして約20枚なので、1枚5000円の原稿料だと、この執筆労働は、時給10万円になる。(P.28「第1章 原稿料と印税」)
もちろん、これは純粋なタイピング時間のみを切り取った数字である。
実際の創作活動には、推敲や修正といった作業も含まれる。
それらをすべて考慮に入れると、最終的な時給は5万円程度に落ち着くかもしれない、と彼は冷静に付け加えている。
それでもなお、高度な専門性とスキルを持つプロフェッショナルの労働価値が、いかに高いものであるかを雄弁に物語っている。
本の価格と印税率の現実
単行本が出版された際の収入の柱は、ご存知「印税」である。
これは、本の定価に一定の「印税率」を掛け、さらに発行部数を掛け合わせた金額となる。
この印税率もまた、作家の実績や交渉によって変動する。
普通の書籍の場合は、僕が聞いた範囲では、印税率は、本の価格の8%~14%の範囲であり、僕自身が経験したのは、最低が10%で最高が14%だった。(P.33「第1章 原稿料と印税」)
一般的に、新人作家は10%からスタートすることが多いと言われている。
仮に定価1,500円の本が初版1万部で発行されたとすると、作家の印税収入は150万円(1,500円 × 10% × 1万部)となる。
しかし、ここには出版業界の構造的な、そして厳しい現実が存在する。
それは、世に出る書籍の大半が、出版にかかったコストを回収できずに赤字になっているという事実だ。
出版社は、一部のベストセラーが生み出す利益によって、その他多くの書籍の赤字を補填している。
つまり、作家の印税は、出版社の大きなリスクと投資の上に成り立っているのである。
この構造を理解しているからこそ、森博嗣は読者に対して媚びるような姿勢を一切見せない。
彼のスタンスは、プロとして一貫している。
僕は、「本を買って下さい」と言ったり書いたりしたことは一度もない。読者に対して望むことは、本の値段よりも多くの価値が貴方にとってありますように、ということだけである。これは、大部分は相性の問題なので、いかんともしがたいといえるだろう。(P.53「第1章 原稿料と印税」)
この言葉は、彼の作家としての絶対的な矜持と、読者への誠実な想いを示している。
彼は、自分の作品が読者にとって価値あるものであることを願うだけであり、購入を強制するようなことはしない。
この一見突き放したような姿勢こそが、逆に多くのファンを惹きつけ、信頼を勝ち得てきた要因なのかもしれない。
印税だけではない多様な収入源
作家の収入は、原稿料や印税だけにとどまらない。
知名度と影響力が高まるにつれて、その活動は多岐にわたり、収入源もまた多様化していく。
森博嗣は、自身が経験した特殊なケースについても具体的に紹介している。
また、ある清涼飲料水メーカから小説を依頼されたことがって、このときの原稿料はその1作で1000万円だった。その作品は本になって出版されたのだが、そのときの印税とは別にである。これは原稿料というよりも広告料と捉えるのが正しいかもしれない。(P.59「第1章 原稿料と印税」)
これは、企業のプロモーションの一環として小説が執筆された、いわゆるタイアップ企画の例だ。
作品そのものの価値に加え、人気作家が関わることによる広告・宣伝効果が評価され、破格の原稿料が支払われたケースである。
現代において、作家がコンテンツクリエイターとして、またインフルエンサーとして企業と協業する可能性を示唆している。
また、他の作家の著作に関わることで収入を得る機会もある。
例えば、対談への参加だ。
彼は、自身がファンであると公言する解剖学者の養老孟司(ようろう・たけし、1937年~)の著作に参加した際のエピソードを語っている。
養老先生の著作は、かなり以前から多数読んでいて、僕はファンである。それで、オファがあったときにすぐに引き受けたのだが、この本では、対談をした4人に1%ずつの印税が支払われる条件になっていた。(P.63「第1章 原稿料と印税」)
憧れの人物との仕事であると同時に、そこには明確なビジネスとしての契約が存在する。
印税をどのように配分するかという内幕は、コラボレーションという仕事の実際を知る上で非常に興味深い。
ちなみに、森博嗣が参加している養老孟司の著作は『文系の壁 理系の対話で人間社会をとらえ直す』である。
その他にも、自身の作品が大学の入学試験問題に使用された場合の使用料も収入となる。
僕は、日本文藝家協会が規定している料金をいただくことにしている(ちなみに、日本文藝家協会の会員ではない)。(P.65「第1章 原稿料と印税」)
その額は一件あたり1000円から2000円程度と少額だが、自身の作品が知的財産として公に認められ、価値を生み出していることの証左と言えるだろう。
プロとして仕事を獲得し続けるための戦略
このように多様な収入源を持つ作家だが、一度成功したからといって安泰なわけではない。
継続的に仕事を獲得し、プロとして生き残り続けるためには何が必要なのだろうか。
森博嗣の考えは、徹頭徹尾、明快かつ合理的である。
価格に見合わせない高品質な仕事をして、割が合わないと感じても、それは宣伝費だと理解すれば良い。最も大事なことは、多作であること、そして〆切に遅れないこと。(P.72「第1章 原稿料と印税」)
目先の利益にとらわれず、常に質の高いアウトプットを心がけること。
それが未来の仕事につながる最も効果的な「宣伝」になるという考え方だ。
そして、プロフェッショナルとしての信頼の根幹をなすのが「多作」と「締切厳守」。
出版社からすれば、才能はあっても締め切りを守らない作家より、コンスタントに質の高い作品を納期通りに上げてくれる作家の方が、ビジネスパートナーとして計算が立つのは自明の理である。
彼は、仕事の価値を自身でコントロールすることの重要性も説く。
例えば、文庫本の巻末に収録される「解説」の仕事だ。
文庫の解説は、その一文に対して普通は10万円程度の原稿料が設定されている。不思議なことに、これは文章量には関係なく定額である。(P.73「第1章 原稿料と印税」)
この業界の慣習的な相場に対し、彼は自身の基準を設け、交渉に臨む。
そこで、あるときに、僕はこの解説の原稿料を25万円に引き上げることにした。10万円ではやれない、という判断である。25万円もらえれば、必要な時間と量力に見合った仕事だと考えたからだ。それに、未読のものであれば、読んだあとに断れることを条件にした。(P.74「第1章 原稿料と印税」)
自分の仕事の価値を安売りせず、正当な対価を要求する。
そして、質の低い仕事にならないよう、内容を吟味した上で断る権利も確保する。
この毅然とした態度は、組織に属さず、自らのスキルで価値を提供するフリーランスとして働くすべての人にとって、大いに参考になるだろう。
ちなみに、本の帯などに書かれる短い推薦文の料金は、2万円から3万円が相場だという。
デジタル化とグローバル化の波
出版業界もまた、デジタル化とグローバル化という大きな変化の波に直面している。
電子書籍の普及は、作家の収入構造にも影響を与え始めている。
現在では、電子書籍の印税率は15%~30%が多いようだ。(P.80「第1章 原稿料と印税」)
これは、紙の書籍と異なり、印刷費や製本費、倉庫での保管費用や物理的な流通コストがかからない分、作家への還元率が高く設定されているためだ。
読者にとっても、作家にとってもメリットのある形態と言えるだろう。
また、作品が海外で翻訳出版される場合、新たな印税収入が生まれる。これは作家にとって大きなチャンスだ。
ここで、印税の割合をどうするのかはそれぞれの契約によるが、僕が経験したものでは、原作者と翻訳者で折半、つまり50:50で分けるのが普通のようだ。(P.83「第1章 原稿料と印税」)
翻訳出版にあたり、森博嗣が唯一出したという条件が非常に興味深い。
翻訳のオファがあったとき、僕の場合は、森博嗣のローマ字表記を「MORI Hiroshi」にすることくらしか条件を出していない。(P.83「第1章 原稿料と印税」)
これは、英文学者の斎藤兆史(さいとう・よしふみ、1958年~)などが提唱する、姓を先にする日本古来の表記方法である。
欧米の慣習に合わせるのではなく、グローバルな舞台においても、自身の文化的アイデンティティを大切にするという、静かながらも強い意志の表れである。
このような収入の話と並行して、彼は「作家の名前を売る」ことの重要性を繰り返し説く。
「作家の名前を売る」ということは、作家自身が考えなければならない最重要課題である。(P.89「第1章 原稿料と印税」)
「本を買って下さい」とは決して言わない彼が、自身のブランド価値を高めるためのマーケティング活動は怠らない。
この一貫した戦略的思考こそが、彼を長きにわたる成功に導いた要因の一つだろう。
サイン会は誰のため?ドライな分析眼
作家の活動は、書斎での執筆だけではない。
講演会やサイン会といったイベントも、読者と交流する重要な仕事の一部だ。
しかし、森博嗣はこれらのイベントの効果に対しても、極めて冷静で、ともすれば冷笑的とも取れる分析を加える。
特にサイン会については手厳しい。
書店は、本が100冊売れるが、この利潤は数万円だろう。出版社の人もスタッフとして駆けつける。みんな仕事をしたつもりになっているのだが、宣伝効果はほとんどないといって良い。ただ、書店の店長が、作家を呼ぶ力があると誇示できる、というくらいがメリットである。(P.101「第2章 その他の雑収入」)
ファンにとっては作家と直接会える嬉しいイベントであるサイン会も、ビジネスの視点から見れば、関わる人々の労力に対して宣伝効果が低く、費用対効果に見合わない、と彼は断じる。
無駄を徹底的に嫌い、常に合理性を追求する彼らしい視点であり、物事の裏側にある力学や本質を鋭く突いている。
メディアミックスがもたらす利益
小説がドラマ化や映画化される、いわゆるメディアミックスは、作家に大きな利益と名声をもたらすイメージがある。
実際のところはどうなのだろうか。
小説がドラマになる場合、1時間の放映に対して50万円くらいの額である。(P.116「第2章 その他の雑収入」)
1クール10話の連続ドラマであれば、500万円の放映権料が原作使用料として入る計算だ。
メディアミックスは、原作の知名度を飛躍的に高め、書籍の売上を押し上げる効果も絶大だ。
作品という一つの資産が、多角的に展開することで新たな価値を生み出し、収入源もまた多様化していくのである。
余談だが、元大学教員である彼は、こんなユニークな経験もしている。
僕は、実際に大学の入試問題を何度も作った経験がある(国語ではなく数学だったが)。(P.141「第2章 その他の雑収入」)
小説家としてだけでなく、工学者としての顔も持つ彼ならではのエピソードだ。
このような多面的でユニークな経験が、他の誰にも真似できない、彼の作品世界の深みと独自性を形成していることは間違いない。
作家は生き残れるか?未来への提言
出版不況が叫ばれて久しい現代において、作家という職業の未来を不安視する声は少なくない。
森博嗣は、これからの作家に何が必要だと考えているのか。
彼の答えは、本書の中で繰り返し述べられてきたことの、力強い再確認である。
だが、とにかく作品をまず書くこと、しかも何作も量産することが先決というか大前提である。(P.189「第4章 これからの出版」)
結局のところ、作家の価値は作品によってのみ示される。
小手先のマーケティングや宣伝活動ではなく、質の高い作品を、途切れることなくコンスタントに生み出し続ける「多作」。
それこそが、変化の激しい時代を生き残るための唯一にして絶対の道だという、彼の揺るぎない信念がここにある。
スランプとは無縁の執筆哲学
多くの作家やクリエイターが苦しむ「スランプ」。
書きたくても書けない、アイデアが枯渇するという産みの苦しみは、創作活動につきものだと考えられている。
しかし、森博嗣はその経験がキャリアを通じて一度もないと断言する。
その理由が、彼の仕事観を最も象徴しており、非常に示唆に富んでいる。
「書けなくなる」ということがあるらしい。僕は、その心配をしたことがないし、スランプというものを経験したこともない。どうしてかといえば、僕は小説の執筆が好きではない。いつも仕事だからしかたなく嫌々書いている。小説を読む趣味もない。この仕事がさほど好きではないし、人に自慢できる価値があるとも認識していない。スランプにならないのは、このためだと思う。(P.196「第4章 これからの出版」)
これは、多くの人が抱く作家像を根底から覆す、衝撃的な告白である。
「好きではない」「嫌々書いている」。
しかし、これは決して自身の仕事に対するネガティブな感情の吐露ではない。
彼は、執筆を「好き」か「嫌い」かという感情のレイヤーで捉えるのではなく、あくまで遂行すべき「仕事」として客観視しているのだ。
感情の波に創作活動を左右されることなく、プロフェッショナルとして淡々とタスクをこなす。
だからこそ、情熱の枯渇といったスランプに陥ることなく、驚異的なペースで作品を量産し続けられるのである。
この姿勢は、あらゆる職業人にとって、仕事を長く継続していく上での大きなヒントとなるだろう。
19年で15億円。数字が語る成功の軌跡
あとがきで、森博嗣は自身のキャリアを、極めて具体的な数字で総括している。
デビューして今年(2015年)の4月で19年になる。その間に国内で印刷出版した本は、278冊、総部数は約1400万部、これらの本が稼いだ総額は約15億になる。1冊当り約5万部が売れ、約540万円を稼いだ計算になる。(P.199「あとがき」)
278冊、1400万部、15億円。
これらの圧倒的な数字は、彼が本書で語ってきた仕事哲学が、単なる机上の空論や理想論ではなく、確かな結果に裏打ちされた、極めて実践的な方法論であることを何よりも雄弁に証明している。
浮き沈みの激しい作家の世界で、これだけの長期間にわたってコンスタントにヒット作を生み出し続けた彼の軌跡は、まさに圧巻の一言に尽きる。
まとめ:成功の条件は「自己矛盾」にある
本書を締めくくるにあたり、森博嗣は成功の本質について、深く、そして鋭い洞察を披露している。
それは、彼の生き方そのものを体現するような言葉だ。
大勢を相手にするビジネスだから、認めてもらわなければ成り立たない。そこへ、認めれれなくても良いものをぶつけていけ、という矛盾した話である。どんなジャンルでもそうだが、結局、なんらかの自己矛盾を持っていることが成功の条件でもある。(P.203「あとがき」)
大衆に迎合するだけでは、心に深く刻まれるような作品は生まれない。
かといって、独りよがりな自己満足に終始する作品では、誰にも受け入れられず、ビジネスとして成り立たない。
市場のニーズや時代の空気を冷静に理解しつつも、それに安易に流されることなく、自身の信じるもの、表現したいものを貫き通す。
この緊張感をはらんだ「自己矛盾」を内包し、作品として昇華させることこそが、多くの人を魅了する傑作を生み出すための必須条件なのかもしれない。
『作家の収支』は、作家という職業の経済的な側面を詳細に解き明かすだけでなく、森博嗣という一人の類い稀なプロフェッショナルの思考法、仕事術、そして人生哲学に深く触れることができる、唯一無二の一冊である。
お金の話に興味がある人はもちろん、自らの仕事に誇りを持ち、その価値をいかにして高めていくべきか悩むすべての人に、強くお勧めしたい。
- 森博嗣『新版 お金の減らし方』要約・感想
- 森博嗣『孤独の価値』要約・感想
- 森博嗣『読書の価値』要約・感想
- 森博嗣『勉強の価値』要約・感想
- 森博嗣『諦めの価値』要約・感想
- 森博嗣『悲観する力』要約・感想
- 森博嗣『アンチ整理術』要約・感想
- 森博嗣『小説家という職業』要約・感想
- 森博嗣『集中力はいらない』要約・感想
- 森博嗣『自分探しと楽しさについて』要約・感想
- 森博嗣『自由をつくる 自在に生きる』要約・感想
- 森博嗣『夢の叶え方を知っていますか?』要約・感想
- 森博嗣『「やりがいのある仕事」という幻想』要約・感想
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:エッセイや随筆など
- 【選書】森博嗣のおすすめ本・書籍12選:推理小説など読む順番も
- 【選書】京極夏彦のおすすめ本・書籍12選:小説、電子書籍も
- 【選書】京極夏彦のおすすめ本・書籍12選:エッセイや随筆、対談集など
- 【選書】夢枕獏のおすすめ本・書籍12選:代表作などの小説
- 【選書】夢枕獏のおすすめ本・書籍12選:エッセイや随筆など
- 【選書】今野敏のおすすめ本・小説12選
- 【選書】逢坂剛のおすすめ本・小説12選
- 【選書】佐々木譲のおすすめ本・小説12選
- 【選書】北方謙三のおすすめ本12選:ハードボイルド小説
- 【選書】宮部みゆきのおすすめ本・書籍12選:時代小説など
- 【選書】宮部みゆきのおすすめ本・書籍12選:現代小説、ミステリーなど
- 【選書】大沢在昌のおすすめ本・小説12選
- 【選書】横山秀夫のおすすめ本・書籍12選:警察小説など
- 【選書】東野圭吾のおすすめ本・書籍12選
- 【選書】白川道のおすすめ本・小説12選
- 【選書】新堂冬樹のおすすめ本・小説12選
- 【選書】新田次郎のおすすめ本・山岳小説12選
- 【選書】五木寛之のおすすめ本・小説12選
- 【選書】伊集院静のおすすめ本・小説12選:読む順番も解説
- 【選書】宮本輝の小説のおすすめ本12選
- 【選書】冲方丁のおすすめ本10選:SF、歴史小説、ミステリーなど
- 【選書】葉隠のおすすめ本10選+番外2選:現代語訳や解説書、小説も